[おくすり編]2017年3月2日
災害時の薬剤師の役割について! |
|
2017年2月23日
薬剤師さんの地域貢献活動について☆今週は、栃木県薬剤師 副会長の 渡邊和裕さんに 薬剤師さんの地域貢献活動についてうかがいました! 今後の薬局のあり方の方針として 平成27年10年 厚生労働省から打ち出された 「患者さんのため薬局ビジョン」。 薬剤師さんは、これから 薬局で調剤業務だけを行うのではなく もっと 地域へ出かけて 地域の皆さんの 健康サポートをする役割を担っていくことが求められています。 例えば 学校薬剤師として子どもたちの学校保健の向上に携わること。 薬物乱用防止のために 学校で子どもたちにお話しをしたり 地域のかたへもお伝えする機会が設けられています。 そして 最近 ニーズが増えているのは、 いわゆる“出前おくすり講座”! 地域の自治会の集まりや、地域包括支援センターなどで 高齢者に向けての健康法や お薬相談会も 各地域で 保健所さんなどからの依頼を受けて開催しているそうです。 今後、色々な場面で 薬剤師さんに出会うことが増えそうですね! 健康のこと、薬の事、病気のことなどで 不安や分からないことがあったら かかりつけ医と連携を取りながら対応してくれる 薬剤師さんに、気軽に相談してみましょう! |
|
2017年2月16日
たばこの害について。(…チェーホフの戯曲ではありませんよ、笑) 今週は、栃木県薬剤師会 副会長 渡邊さんに 「たばこの害」について聞きました! たばこの害については 近年、ずいぶん叫ばれて 公共の場では 分煙・禁煙が進んでいますが 健康によくないことはモチロン… 美容の大敵でもあるということ! たばこの煙に含まれるニコチンを解毒するために 体内ではビタミンCが消費されます。 ビタミンCと言えば、美しいお肌の維持に必要な栄養素… たくさんたばこを吸うとビタミンC不足がおこって 肌荒れが起きたり シワが増えたりしちゃうこともあるそうです~ 街の薬局では 禁煙をサポートしてくれるそうですよ! 禁煙を始めたい方、 禁煙中のお悩みがある方も 身近な薬剤師さんに相談してみてくださいね! |
|
2017年2月9日
薬物乱用 について。今日は 栃木県薬剤師会 渡邊和裕さんに 「薬物乱用」について お話していただきました。 覚せい剤 大麻 コカイン LSD マジックマッシュルーム MDMA… 法で規制され 所持 売買はもちろん 一度でも 使用すれば 薬物乱用となる 薬の数々。 また、シンナーなど有機溶剤や各種ガスは それぞれの用途のために販売されているもので これらを吸引することは目的の逸脱になりますので、 これも薬物乱用となります。 また、身近に手に入りやすい睡眠薬・鎮痛剤なども 用法 容量を守らずに使用することで 薬物乱用となることがあります。 また 覚醒剤など法で規制された薬物、そして 危険ドラッグによる事件・事故の発生は 栃木県内でも少なくないそう。 そして そうした薬物の使用が 若年化・低年齢化しているということも とても心配なことです。 そのため、薬剤師会では 様々な場所で 薬物乱用防止の啓発活動を 随時おこなっているそう。 薬物乱用によって 失われるものは 自身の健康だけではありません。 その社会的な影響も 想像以上です。 薬物の入る 心の隙を 持たないこと。 何が何でも 使用しない!という勇気。 これからも 持ち続けていきたいですね。 |
|
2017年2月2日
学校薬剤師…って!?今夜は、栃木県薬剤師会 副会長 渡辺和裕さんに 「学校薬剤師」のお仕事と役割についてうかがいました。 学校薬剤師は、自治体の教育委員会によって 各学校に一人、薬剤師会から派遣(委嘱)されている薬剤師さん。 経験と知識の抱負な薬剤師さんが指名されています。 …給食室、家庭科室、 保健室、プールなどの衛生検査… 環境衛生という面では、照明の明るさのチェックなども 行なっているそうですよ! そして、子ども達に お薬にまつわる “出前授業”などを行なうのも大事なおしごと。 最近では 危険ドラック・薬物乱用についての 注意喚起などのお話も されているそうです。 通常の薬剤師さんとしてのお仕事に加えて 学校の空いている時間に 学校を訪れ、 こうした検査などを行なうということで 大変なんじゃないかな~と思いましたが… 「子どもたちの健康を守る、 大切で、名誉ある、やりがいのある仕事です!」 カッコいいですね~!(^^) そんな学校薬剤師さん、近ごろは高齢化もあって 担い手が不足気味とのお話も…。 ぜひ“興味があるよ~”という 栃木県内の薬剤師さんは 渡邊会長まで、ご連絡してみてください! |
前のページ 次のページ
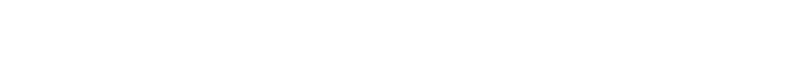










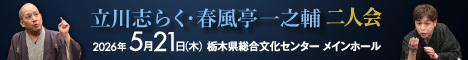



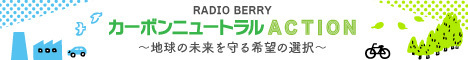

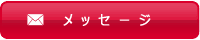
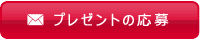
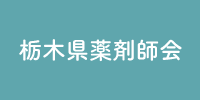
今回は 栃木県薬剤師会 会長 大澤光司さんに
「災害時の薬剤師の役割」についてうかがいました!
東日本大震災の時、何度か被災地に入ったという大澤さん。
救援物資として送られてくる医薬品の整理、
避難所に設置される臨時診療所での調剤、
被災者の健康相談。
人々の健康を維持するための
大切なお仕事についてうかがいました。
そして、東日本大震災の教訓から生まれた
「モバイルファーマシー」。
キャンピングカーに、たくさんのお薬と調剤のための道具一式が
積まれている、災害時に活躍する“移動薬局”です。
まだまだ 全国で数台しか無いそうですが
大澤会長は「ぜひ栃木県にも!がんばります!」
いつ使うか分からない、でも 絶対に必要な“備え”。
モバイルファーマシーについては、次回も詳しくうかがいます。