[MY TOWN なかがわ(2014年3月放送終了)]2012年4月26日
#30 水戸黄門ゆかりの「 たけのこ祭り 」 たけのこ祭りとは、
馬頭地区の氏神様 静神社の春季例大祭の別称で 旧暦5月の季節に 氏子たちがタケノコを煮て食べ、 例祭参拝に来た人に振る舞ったことから この名前が付きました。 当日は、静神社から神様に降りてきていただき、 町内を神輿で渡御します。 担ぎ手は、白丁( はくちょう:白い装束 )に 黒い烏帽子をかぶり 太鼓の音に合わせて、ゆっくりと静かに町内を練り歩きます。  その列には当番町の屋台も加わり、
列の長さは 何と50mほどにもなるそうです。 当番町とは、たけのこ祭りを仕切る町のことで、 1年ごとに新町・田町・南町・室町の それぞれの町が当番となり、 各町の屋台を出します。(今年の当番は新町) その町に残る屋台彫刻は、 日光東照宮造営宮大工の彫刻の流れをくむもので、 その美しさには、目が奪われてしまいます。 さらに、たけのこ祭りでは 屋台の前に舞台をすえ 余興の歌や踊りが演じられます。 この舞台が他に類をみないもので、 民俗学的にも価値の高いものとされています。  伝えられるところによると、
話は江戸時代に遡ります。 水戸黄門でおなじみの水戸光圀公が、 たけのこ祭りを見に来られておりました。 その日は 日差しの強い中で、 娘手踊りをご覧になった光圀公は 「何か日差しを遮るものはないのか」 と命ぜられました。 即座のことで、馬頭院の仏事用の白黒の幕しか用意できず これを天幕として利用しました。 しかし、これだと白黒になってしまうと 当時の世話人の粋な図らいで 若衆がつけていたピンク色のタスキを 白黒の天幕の上からかけたそうです。 これを「御免天幕」といい 今日でもこの形が残っています。 白と黒とピンクの舞台・・・・。 なかなか見ごたえがあります。 精巧な彫刻屋台に舞台、そして御出社・御帰社と 様々な見どころがあり、目を楽しまさせてくれるお祭りです。 水戸光圀公 ゆかり の 極めて古く、その形が今やなお残る伝統的なお祭りに ぜひ 足を運んでみてください。  ※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※
5月1日(火) 御出社 ◆16時~ 静神社より神輿と本屋台行列での御出社 5月1日(火) 余興庭割、本屋台巡行と御帰社 【民謡と踊り】 茨城県磯節保存会・福田佑子 外のみなさん ◆10時30分 / 11時30分 / 12時30分 14時 / 19時30分 ~ 【お囃子演奏】 鷲子囃子保存会のみなさん ◆11時30分 ~ 【御帰社・金棒引き】 ◆16時~ 御仮屋より神輿と本屋台行列での御貴社 金棒引き(稚児行列) ◆20時~ 屋台に提灯を飾り、町内巡行 ※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※*※ |
次のページ













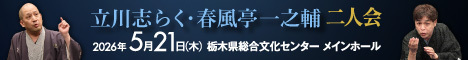

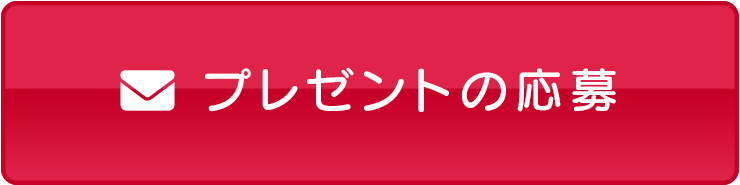
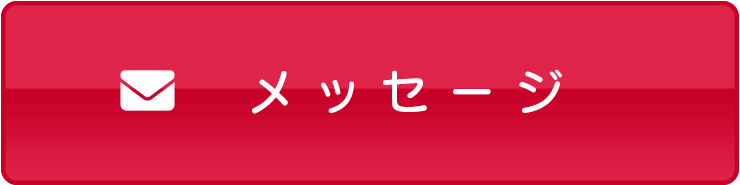



那珂川町で古くから続く
伝統的なお祭り 「たけのこ祭り」が5月1日・3日
馬頭中心商店街を会場に行われます。
このお祭りの執り行い方、屋台、舞台には
“めずらしい云われ”があるようです。
果たして、その云われ・歴史とは?
町内外問わず、必見のお祭りです。
゚・。+☆+。・゚・。+☆+。・゚・。+☆+。・゚・。+☆+。・゚・。+☆+。・゚・。+☆+。・゚