[キラリ!日光]2013年12月12日
しもつかれ料理教室に行ってきました! お話しを伺ったのは、日光市農村生活研究グループ協議会 会長の竹澤早苗さん(写真↓右)。栃木の郷土料理しもつかれは、初午の日にお稲荷さんにお供えする際に作られます。そもそもお稲荷さんとは、日本の神様の一つで、農業や食の神様のことだそうです。そのお稲荷さんの誕生日とされるのが、二月の初午の日。今年は2月4日(火)。お稲荷さんの使者である狐の好物とされる、油揚げや油揚げに寿司を詰め込んだお稲荷さんなどを奉納する習慣が、今でもあるそう。
初午の前の日2月3日節分に大豆を撒く→大豆がしもつかれの材料になる。初午の日はお稲荷さんを作る→油揚げがしもつかれの材料になる。こんな風に、人々の生活の流れがあって、郷土料理しもつかれは生まれたのだそうです。  今回作ったレシピを紹介します。
材料:大根2㎏、人参300g、いり大豆80g、油あげ2枚、塩鮭の頭小1個(200g程度)、酢大さじ2、水400cc、酒粕100~150g、しょうゆ適量、塩適量、砂糖(お好みで)。 作り方: ①鮭の頭はよく洗い、2㎝くらいの角切りにして湯でこぼし、臭みをとる。 ②圧力鍋に①と酢と水を入れ、20分ほど煮る。 ③大根、人参は鬼おろしでおろす。 ④いり大豆は布巾に包んで揉み、皮をとり除く。 ⑤油あげはうすく焦げ目がつくくらいに焼き、縦半分にしてから細切りにする。 ⑥酒粕は小さくちぎり、熱湯に浸してやわらかくしておく。 ⑦厚めの鍋に、②③④⑤をいれ、はじめ強~中火にかけ、ぐつぐつ煮えてきたら弱火にして1時間ほど煮込む。 ⑧味がなじんできたら⑥を入れ、しょうゆ、塩で味を調える。  ポイント:塩鮭の塩気によって、しょうゆ、塩の分量は加減することと、塩鮭の頭は焼いてから使っても良い。材料の分量は自分の好みにかえてもよい。生大豆を使うときは、水に浸してから②のときに一緒に煮ること。・・・だそうです!
鬼おろしでガリガリガリガリ・・・根気のいる作業です。  で、あっという間に出来上がったしもつかれ。味付けは先生の作ったお手製お味噌を少々入れただけ。皆さんが口を揃えておっしゃるのは、「自分で作ったしもつかれが一番美味しい!」。・・・一緒に作ってくださったみなさん、本当にありがとうございました。
二月には、今市で毎年行われている全日本しもつかれコンテストがあります。今回の作り方を家で復習して、家族の好評を得られる腕前になったら、私も挑戦してみたいです。 つい先日、世界無形文化遺産に登録された和食。その伝統文化を守り、次の世代へ伝えていくために、今、私たちにできることは何だろうと、食生活を見直すきっかけになりました。 美味しいごはんの先には、きっと、みんなの笑顔が待っているはずです♪♪♪  |
前のページ 次のページ















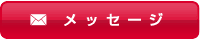
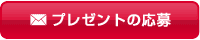
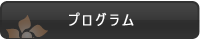
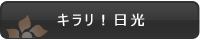
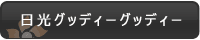
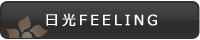

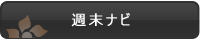
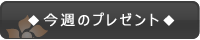

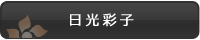


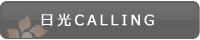
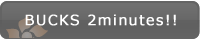

毎月日光市民のお手元に届く「広報にっこう」の裏表紙。そこに毎月、日光のおいしいレシピを紹介しているのが、こちらのグループ。農家のお嫁さんたちが主体となって、栃木県の郷土料理しもつかれを教えてくれるお料理教室が先日、今市にある大沢公民館(写真↓)で行われました。