[今月のエコピープル]2021年7月2日
日本両棲類研究所 所長 篠崎尚史さん 両生類は、生物の中でも環境に対して非常に敏感な生き物で、 少し環境が汚染されるだけでも 数が減ったり、 姿を消してしまうため、生態学では 「環境指標動物」と言われているそうです。 つまり、両生類を観察していると、 環境の変化が見えてくる…ということなんですね! そして 良い自然環境を残すためには、 両生類が“生き続けられる”ような環境を提供する…、 もし人が開発を進める場合にも、 水質や、周囲の緑など 両生類の棲み処を守りながら開発をおこなう…、 それが 篠崎さんの 自然保護分野のお仕事だそうです。 両生類…と聞いて 皆さんがイメージするのは どんな生き物でしょうか? もしかしたら 苦手な方もいるかも知れませんが(汗)、 実は とってもスゴイ生物だったんですね…!! |
|
2021年6月1日
藍生産農家「藍百姓 藍松」 松由拓大さん 「藍百姓 藍松」 松由拓大さんは、栃木県矢板市で 藍染めの原料となる 蓼藍(たであい)を栽培する 生産農家。 世界で“ジャパンブルー(ジャパニーズブルー)”と呼ばれる 藍の魅力を伝えながら、藍を育てる人・栽培面積を増やすための 活動にも力を入れていらっしゃいます。 また、藍の栽培風景が登場する 2021年のNHK大河ドラマ 『青天を衝け』では、藍作指導も 担当されました!!  松由さん、いろいろ見せてくださいましたよー!! 藍の種や、藍の葉を乾燥させたもの、 蒅(すくも)、蒅をつくるために必要な木灰、 ふすま(麦のぬか)なども。 …藍染めに使われる原料は、 今でいうところの 再生可能な資源なわけで…。 先人たちの知恵って スゴイなぁ~!! 松由さんも、 「いまだに 不思議です。 どうしてこの葉っぱから あの青が出るのか。」 …ほんとですよねぇー。  ↑須賀ちゃんが持っているのは、藍を混ぜた 泥だんご。 青が美しくて…まるで宇宙から見た地球みたい…! (本物は見たことナイけどー!笑) そのほかにも、藍の種のプチプチ感がおいしい焼き菓子 (芳賀町にある「古賀洋菓子店」さん作!)や、 藍の成分が入った のど飴もご紹介いただきましたよ♪ …松由さんとお話していると 藍の計り知れない可能性を感じます…! * でも、この藍…、 松由さんによると、現在 日本国内での栽培は 合わせて24ヘクタールまで減っているそう。 (衝撃!) そして、天然の(“化学藍”でない)藍染めは、 たいへん貴重なものになっています。 このままでは 天然の藍がなくなってしまう… 「焦ってるんです!」と松由さん。 そこで 現在は、藍の魅力や様々な用途を伝える活動、また、 “藍百姓”として生計を立てられる人を増やすための仕組みを 模索中とのことです。 県内の幼稚園や小学校では、アサガオのように、 子ども達に藍を育てる体験も広めていらっしゃいます。 (小さな鉢でも 藍は育つんですって…! しかも 栃木県の気候は 栽培しやすいのだとか。) ↓こちらの写真は 藍の種。 この種たちによって どんな未来が創られていくのかしら…と 想いを馳せつつ、、、私たちも かつての日本人のように、 生活の中に もっと藍を身近に感じられたら良いなぁと思います。 藍の種は、「藍松」のHP内でも 販売中! 気になった方は ぜひチェックしてみてください☆  |
|
2021年5月7日
戸祭山緑地ワーキンググループ「レッドパイン」会長 岡田喜三さん 『レッドパイン』は、 「公益財団法人グリーントラストうつのみや」が保全する 「戸祭山緑地」で活動するボランティアグループ。 戸祭山緑地は、日光・今市方面から連なる 宇都宮丘陵の南端にあって、広さ:およそ26.0 ha、 標高:130~170m、高低差:およそ40mという、アカマツ林や コナラ林など 全体が樹木に覆われた 小高い森です。 宇都宮競輪場のすぐ北側、宇都宮市の中心部から北へ 約2㎞の位置にある森ですが、宇都宮市の天然記念物に 指定されている「トウキョウサンショウウオ」など 貴重な動植物が生息し身近に自然を感じることが 出来る場所です。緑地の散策コースは 一周約2,2㎞、 「レッドパイン」の皆さんの活動によって 歩きやすく整備されています。一部勾配もあって、 のんびり歩くだけで良い運動になりますよ♪ 野鳥の声と豊かな緑に包まれながら、 皆さんも散策してみてはいかがでしょうか。 |
|
2021年4月1日
「株式会社ジェム・テクシア」 長坂五郎さん 長坂洋子さん 株式会社ジェム・テクシアは 平成元年設立。 消防設備の施工、建物の放送設備・カメラの施工や 排水設備施工、太陽光発電やLED照明といった省エネ事業施工、 自家発電設備負荷試験、メンテナンス業務を行なう会社です。 その中で、定期的に交換する必要のある 消火栓ホース(消防用ホース)は廃棄される数も多く、 「もったいない!これを何かに再利用できないか?」と 丈夫で防水性のある ホースの素材を活かした トートバッグを考案、地域の縫製業者に依頼し、 製造・販売を行なっています。 この活動に賛同し消火栓ホースバッグを販売する店舗は 県内・外に10ヵ所ほど。 売上の一部は 社会福祉団体へ寄付されるそうです。 さらに数年前からは 廃棄ホースを宇都宮動物園に 寄付され、動物たちの遊び道具になっているそうですよ!  こちらが バッグや小物の材料となる 消火栓ホース! 赤いラインも、金具の部分も よく見るとカワイイんですよね…! 内側はゴムになっていて、水が漏れません。 ゴムの色はメーカーによって緑や青など 様々とのこと。 …確かに… 洋子さん、 これが会社にたくさんあったら 「もったいないなぁ~。有効活用できないかなぁ」と 思いますよねー!  そして トートバッグ♪ こちらでーす! 筒状のホースを切って開き、縫い合わせて作られます。 大きさやマチも、いろいろ試作。 畳の縁などをつかって、ホースの赤いラインが デザインに生かされています! 縁取りのデザインによって、和風になったり ポップになったり 高級感が出たり… 可能性が無限です~!  こちらは 小物たち☆ (ペンケース、小銭入れ、シューズバッグ) 消火栓ホースは シッカリ丈夫な素材なので、 中に入れたものの型崩れがしにくい! そして!!! 最後まで読んでくださったアナタに 長坂さんから プレゼントのお知らせ!! ☆☆☆ 株式会社ジェム・テクシアの ☆☆☆ ☆☆☆ 消火栓ホーストートバッグを ☆☆☆ ☆☆☆ 抽選で3名様にプレゼントします!☆☆☆ (デザインは お任せください) ご応募は「Flying Friday」の応募フォームから 「消火栓ホースバッグ希望」と書いてお送りください。 締め切りは、4月30日(金)まで。 ぜひ皆さんにも使って欲しい、エコでステキなバッグです! ご応募お待ちしています☆ * 株式会社ジェム・テクシアの消火栓ホースバッグは 下記のお店でもお取り扱いがあります。 お近くのかたは是非 チェックしてみてくださいね☆ ・ララカフェ(宇都宮市) ・生活ギャラリー myss(大田原市) ・うなぎ土用亭(鹿沼市) ・鬼怒川温泉旅館 一心館(日光市) ・宇都宮動物園(宇都宮市) ・カモフラージュ(宇都宮市) ・ホリティスジャパン(株)(東京都目黒区) ・丸田商事(株)ゲンキ・キッズ(埼玉県久喜市) ・HARRY TOITO(東京都台東区) * |
|
2021年3月5日
「有限会社ファッションプレス増渕」 増渕弘二さん「有限会社ファッションプレス増渕」は 宇都宮市下栗町にある アパレル会社。 縫製業を中心に、古着の買取販売を行なう 「ドンドンダウン オンウェンズデイ 宇都宮鶴田店」を運営。 2019年頃からは、“古着屋だからできること”の一つとして オリジナルリメイクブランド【CUTaND】を立ち上げ。 【CUTaND】の製品は、役目を終えたデニムを集め、 生地をカットしパッチワークのようにつなぎ合わせて 新しい製品に生まれ変わらせるもので、 デザイン性が高く かつ、リユース素材を活用しながら 物の大切さを伝える取り組みとして、注目されています。  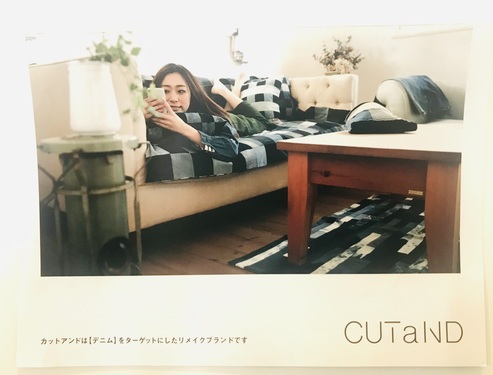  |
前のページ 次のページ














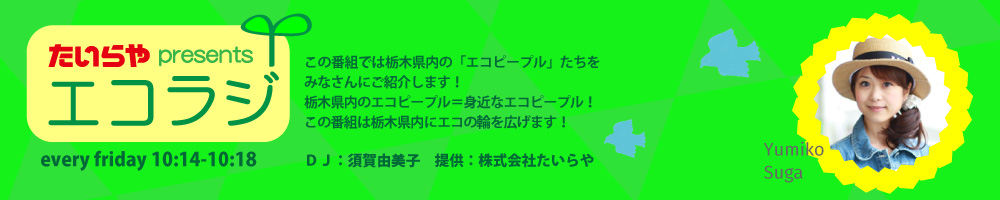
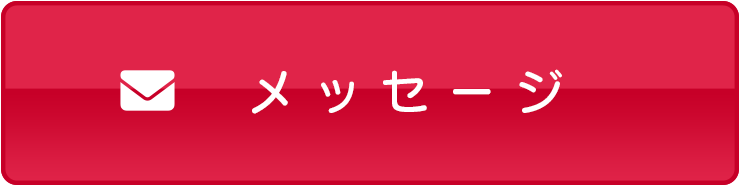

初代所長の 篠崎尚次さんによって設立された 私立研究所。
尚次さんが 戦後の 尾瀬沼(尾瀬原)ダム化に反対し、
日本における自然保護団体の先駆けともなった
「日光の自然を守る会」を設立した事から、
自然保護活動の拠点として 位置付けられた場所です。
研究所は、世界でも有数の
両生類の生息地と言われる 日光にあって、
常時20種類以上の 日本産 サンショウウオ類が
展示・公開される市民の学習の場でもあります。
現在は、尚次さんの息子さんである 尚史さんが所長に。
自然環境調査や、県内の環境アセスメントをはじめ、
繁殖時の轢殺から個体を守る
ハコネサンショウウオ横断トンネルの設置、
人工産卵池の設置など、奥日光における
両生類の保護活動などが行われています。