[MY TOWN なかがわ(2014年3月放送終了)]MyTown #116♪ 火の神宿る「穴窯」 ♪ ちなみにここ松並陶苑の穴窯の外観の写真が
日本で最も美しい村連合のパンフレットに 小砂地区を代表する風景として掲載されています♪ 山の斜面を利用して作られた「穴窯」は幅2m程で 高さはおよそ1m奥行5~6mの細長い奥行きのある鎌倉のような かまぼこ型になっています。 窯の左右の上部には穴が開いていて薪を入れると勢いよく 炎が噴き出します。昼間の迫力もなかなかですが これが夜となれば・・幻想的な雰囲気と銀河へ漕ぎ出して 行きそうな999ほどの迫力すら感じます。 ━─━─[。□□□。][。□□□ 。]━─━─ 小屋の上の煙突からも高い時には2m程の炎があがります。  「登り窯」というのは聞いたことがあっても「穴窯(あながま)」は
御存知ない方も多いのではないでしょうか? 実は登り窯よりも古い時代のもので穴窯でなければ焼けない 作品を作りたいという岡さん .。*(〃´∀`)u 穴窯は登り窯と違って窯の内部に仕切りがなく手前の投入口から 薪を入れて温度を上げます。温度は1150℃から1300℃に保たなければ ならないので薪の投入口から遠い奥の部分は温度が上がりにくいとか。 そこで左右の下部にも投入口があり細めの薪を投入して温度調整をします。 もちろんひとりで10日間も24時間体制で行うわけには いかないので毎回数人の仲間が協力して行われています。 私も薪の投入作業を体験させて頂きましたが まぁこれが熱いのなんの! 1度に数本の薪を入れるのですが投入口から手前にぽんぽんと 手早く投入するのですが・・焼けつくような高温が一瞬にして 襲ってくる感じです。 ・:*・∵.☆:*・∵へ(εoε) 入れる場所をうっかりすると作品が割れてしまうので 充分注意しますが・・どこに作品が入っているのか目視出来ない ほどの熱さでした・・。 薪を入れた後顔の皮膚がピリピリジリジリして目からは涙が!!(笑) (T T)  小砂焼などと違って釉薬を使用しない穴窯での陶芸作品は
手前に入れた薪の熱によって煙突状態の窯の内部で空気の流れが生まれ 捲きあげられた灰が作品について更に土との融合で仕上がる まさに「火の神様が成せる偶然の産物」 ヾ(≧∇≦)/゜ 穴窯に入れた作品のうち1割がうまくいけばいいという岡さん 自然が生み出す素朴で味のある作品と向き合って40年・・ 更にいいものをと焼き続けていきたいという岡さん。 今回岡さんにお願いして私の作った器も入れて頂きました。 これまで作ってきた小砂焼と違う味のある作品になったと思いませんか♪ ゚・*:.。.☆八(≧∇≦〃)v.。.:*・゚ 器の内側はざらっとした感じで外側は見事に光を当てると 紫色を帯びた赤茶色と翡翠の薄いグリーンを帯びた グラデーション・・神様ありがとう!!  穴窯は年2回毎年この晩秋の時期と初夏を迎える6月頃に
火を入れるそうです。 岡さんの作品は松並陶苑で購入できますので是非 炎の神様と岡さんの共同作品をお手に取ってご覧ください♪ .:*・☆・゜・*:.(*^▽^*)ゞ。.*.。.:*・☆ 「松並陶苑」 アクセス:那珂川町小砂2697 定休日 :不定休 問い合せ:0287-93-0936  |
前のページ 次のページ















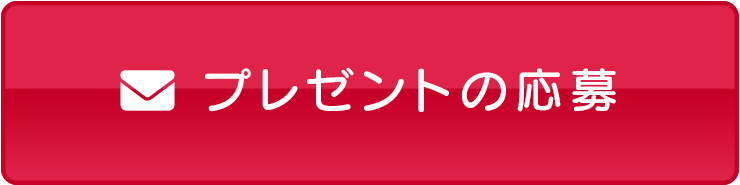
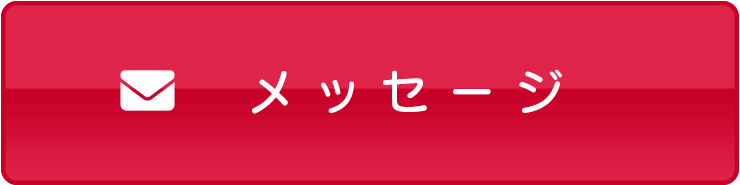



何度もご紹介してきましたが・・実は那珂川町には
小砂焼以外の陶器もあるんです!
今回ご紹介した「松並陶苑」の陶芸家 岡 稔さんの
作品は「穴窯」と呼ばれる窯で作られています。
かつて那珂川町には登り窯や穴窯が何箇所かあったそうですが
年々減り続け残っていた窯も東日本大震災で倒壊してしまい
難を逃れたのは松並陶苑の穴窯のみでした。
窯のある場所は小砂らしい美しく静かな山間。
☆_(*゚∇゚)、。・:*:・゚`★
窯は実に10tにも及ぶという赤松の薪で囲まれています。
年2回火を入れるという窯はおよそ10日間24時間体制で
いっときも休むことなく薪がくべられ、10tもの薪は
全て炎の中へ・・
今回は11月13日~11月23日まで火が入った穴窯に
11月20日にお邪魔してお話を伺ってきました♪
(*’∀’*)/゜:。*。