[なかがわ GOOD リポート(2014年3月放送終了)]2012年1月5日
♪Good 14♪ 七難即滅・七福即生「八溝七福神巡り」 八溝山系国道294号線沿いおよそ37Kmという広い地域の七つの寺院で
七福の神様がおまつりされています。これが八溝七福神! 「七福神」は古くから民間信仰として親しまれきました。 7つの寺院のうち 2つが那珂川町にあるんです♪ 七難即滅・七福即生 これは世の中の七つの大難(太陽の異変、星の異変、風害、水害、火災、旱害、盗難)は たちどころに消滅し、七つの福が生まれるという意味です。 つまりその七つの福=七福神というわけですね♪ 皆さん七福神すべて言えますか? 毘沙門天(びしゃもんてん) 三光寺(那須町芦野) 布袋尊(ほていそん) 不動院 (大田原市久野又) 恵比寿尊(えびすそん) 明王寺 (大田原市黒羽向町) 寿老尊(じゅろうそん) 威徳院 (大田原市湯津上) 大黒天(だいこくてん) 光丸山 (大田原市良土) 弁財天(べんざいてん) 光照寺 (那珂川町小川) 福禄寿(ふくろくじゅ) 乾徳寺 (那珂川町馬頭) 以上7か所の八溝七福神♪ では・・あらためて乾徳寺さんでのお参りをおさらいしましょう♪ まず・・樹齢300年という白藤の下で八溝七福神始まって以来 ずっと続いている手作りの甘酒[//color]をいただきました♪ これは[color=ff00cc]1月7日まで行われています。 甘酒にはお酒は使われていないのでお車の方でも安心して お召し上がりくださいね♪ この白藤は上り藤というもので4月後半から5月前半の藤の季節には 下に垂れ下がるのではなくやや大きめの花房が上めに花開き 香りが境内中に漂うのですが・・この時期はとりあえず想像だけで(笑) そして本堂の前で「縁の綱」という五色の紐を引いてお参りします。 これはお釈迦様の右手と結ばれている紐なのでこの紐を引くことによって お釈迦様と手と手が繋がるということになるのです♪ このお参りの後「身代わり守」というお守りを頂きます。 これは乾徳寺での七福神の参拝記念にこのお正月の時期だけ頂ける 有難いお守りです。頂いたら日頃から持ち歩いたり身の近くに置く などするといいそうです♪  ではいよいよ福禄寿様をお参りします。
まずは礼をしたら手を合わせます。 この時「右手が神様」「左手が自分」として 丁寧に合わせましょう。これで神様と一つになれるのです。 しっかりと福禄寿様を見つめ、ご真言を唱えます。 「南無 福禄寿尊 おん まかしり そわか」 南無というのは帰依するという意味で解りやすく言うと あなたが大好きですよ・・というような意味なのだそうです。 なので神様をお呼びするときは「南無」とつけるとよりよいのです。 このご真言はそれぞれの神様ごとに違う  これでお参りは完了したのでご朱印を頂いきます。
ご朱印帳や色紙などは用意のない方は購入もできますのでご安心を♪ (実は7か所巡れなくても7箇所全ての御朱印が全部揃っている色紙 「満願色紙」というのもありますのでとりあえず行ってみて7か所全部 巡るか考えるのもアリです(笑)) お参りにはその寺院それぞれの手順のようなものが あるらしいのですがお参りのポイント!というのは 基本的にどこも同じなので・・皆さんもお参りを されるときには是非思い出してくださいね♪ 初詣はその土地の氏神様やその年の恵方に当たる神社にお参りする方も 多いと思いますが、様々な福をもたらすという七福神巡り・・ 七福神めぐりはお正月のうち(7日まで)に巡るといいと言われていますが 1年を通していつでもお参りすることができますので ゆっくり時間をかけて八溝の景色を楽しみながら訪れてもいいと思います。 ただし甘酒などの振舞はありませんのであしからず(笑) 色紙にはお参りした年の年号印を押していただけるので いい記念にもなりますよね♪  |
前のページ













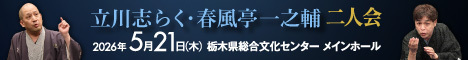

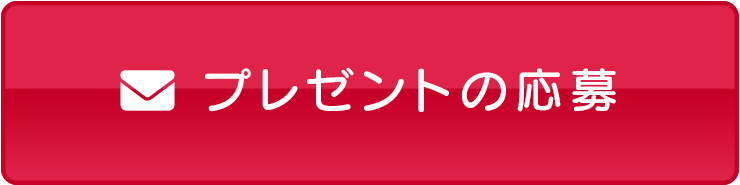
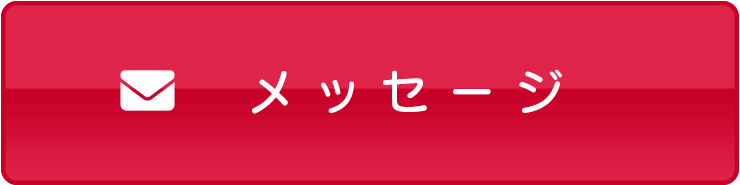



2012年最初ののリポート先は八溝七福神 福禄寿様を
お祀りしている曹洞宗 龍澤山 乾徳寺でご住職と共に
お参りをしてきました♪
春には花観音、秋には見事な紅葉で知られている乾徳寺は
那珂川町馬頭の広重美術館の横にあり、開山(創建)は
今からおよそ550年前頃という古刹で当時の武茂城城主
武茂泰宗の菩提寺です。
そんな歴史ある乾徳寺で44代目ご住職真澄(しんちょう)様に
お参りのお作法などを伺いながら今年の願をかけてきました♪
これで那珂良しラジオも人気上昇!?(笑)