[Let's農!!~たんたんマスターへの道2~]2013年7月24日
~転作調査とは!~ この転作調査という作業と仕組みについて教えてくれたのは、
高根沢町太田にある「農業技術センター 水田農業確立対策室」で働く、 阿久津さん(真ん中)です。さらに、岩本さん(左)も、 作業について教えてくださいました。 転作調査とは、お米の減反調査および、 転作確認を行う、管理作業のことです。 分かりやすく説明すると、 町で、販売するためのお米を栽培する場合、 「○○パーセント、田んぼをお休みして(米を作らないで)ください」 というものが決まっているので、きちんと田んぼがお休みしているか、 そして、その休んでいる田んぼで違った農作物が育てられている場合、 何が育てられているのかを確認しなければならないわけです。  なぜ、田んぼを全部使ってお米を作れないのかというと、
“販売用のお米”は、作りすぎると売れ残ってしまうわけです。 今の時代は、パスタやパン、うどん、蕎麦など、 いろいろな食材がお腹を満たしてくれるので、 必ずしもお米が100%必要な状況ではなくなってきているんですね~。 さらに、出荷量が増えすぎてしまうと、 相場の値段も下がってしまうため、農家さんたちは 「余ってしまう」「安くしか売れない」ということになり、 何の得にもならないというわけです。  つまりは、お米の需要と供給に伴って、
生産量・出荷量を調整する。という作業が きちんと現場で行われているのかどうかを、 確認するんですね~! 農家さんたちの無駄な労働や商売の非効率を押さえるための 立派な町の仕組みというわけです。 そして、その休んでいる田んぼがもったいないために、 「別の野菜を作って利益を得ましょう」ということで 田んぼを転作している場合、その作られている野菜の種類によって 交付金の金額が変わってくるため、しっかり確認する必要があるのです。 この作業は1週間続きます。そして、1日に80~100筆もの田んぼを 見回って、転作確認をするんです。 この地道な作業も、日本の農業の明日を支えているのですね。 |
前のページ 次のページ















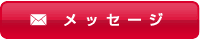
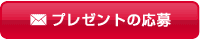
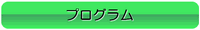
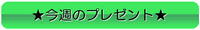
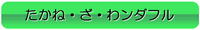
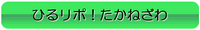
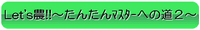
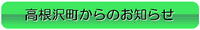
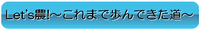
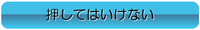
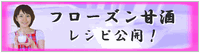
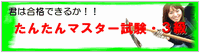
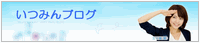
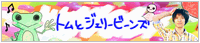



おひさまと、水と、土に感謝しながら
様々な農産物を作ってきた高根沢。
そんな高根沢の農業の魅力を広く伝え、
たんたんマスター見習いとなった
「いつみん」五十嵐愛が、更なる高みを目指し、
日々学び、挑戦、活躍するコーナー。
『Let's 農!!~たんたんマスターへの道2~』
今回は、まちで行っている調査記録の活動である、
『転作調査』というものについて学びました。