[Let's農!~たんたんマスターへの道~]2012年11月7日
~農具展で昔へタイムスリップ~ なんだここは・・・?!伝統的な古民家!
まさか、ほんとに昔にタイムスリップしてきちゃったの?? 古民家の中でお茶を飲んでる人がいたので、 何時代なのか聞いてみたところ… 「2012年の11月7日ですよ。あれ?いつみんじゃないの」 あれ・・・? 全然タイムスリップしてないじゃんー てか、前に城跡探検でお世話になった鈴木さんじゃないかー てことは、ここは歴史民俗資料館ですかー てな具合で、歴史民俗資料館で、 どうやら『農具展』が開かれているらしく、 そこで昔の農業について学ぶということですね!  鈴木さんに農具と昔の農業について教えていただきました!
農具展の会場には、数々の歴史ある農具がたくさん。 全部で59点もの農具があるそうです。  この鍬は備中鍬といって、
昔の人が手作業で田んぼに深く突き刺し、 田をおこすために使用していたもの。結構な重さがありました。 これを立て続けに一日中振り下ろしながら、 お米作りに励んでいたのですね。  こちらの唐箕(とうみ)という機械は、
収獲した籾(もみ)から、ゴミや未成熟の籾を取り除く道具です。 昔は、籾殻を脱穀するのも千歯コキなどで手作業で行ったので、 今のように正確にできるわけではなく、 藁やほこり、未成熟の籾が混じってしまいます。 この道具についているレバーを回すと、 羽根が回転し風が発生します。 その風によって、重さのない未成熟の籾やほこりなどを 吹き飛ばすという原理になっているそうです。 この唐箕も、一度ならず、何度も何度も不要物を取り除き 次第に、精米作業へと移っていくのだそうです。 昔の人たちは、相当な手間暇をかけて作業していたのですね…。 米俵一つにしても、不要な藁で、自家製で作ったんだそうです。 農具展に合わせて、昔の方の農作業の風景写真が飾ってありました。 その人たちは、とてもいい笑顔でした。 苦しいとか辛いなどの表情は見受けられません。 農業は、農具や機械が発展して、今では作業が非常に楽で 効率的になってきています。これも昔の方々の苦労あってのことです。 農業に対する「精神」も、それに甘えず、 日々進化できるように頑張っていきたいと思います! ****************************** 『農具展~なつかしの農具と発動機~』 期間:10月27日(土)~11月25日(日) 場所:歴史民俗資料館(高根沢町石末1825) 休館:月曜日 時間:9:00~17:00 料金:無料 ****************************** |















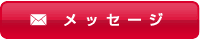
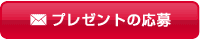
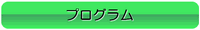
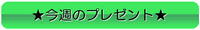
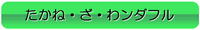
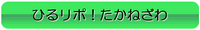
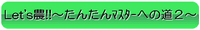
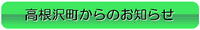
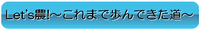
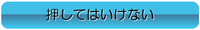
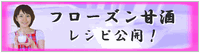
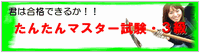
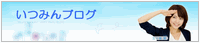
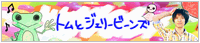



おひさまと、水と、土に感謝しながら
様々な農産物を作ってきた高根沢。
そんな高根沢の
農業の魅力を広く伝えるべく、
パーソナリティ五十嵐愛が
高根沢の農業とその精神を熟知する
「たんたんマスター」を目指し、
学び、挑戦するコーナー。
『Let's 農!~たんたんマスターへの道~』
突然ですが、昔の人たちが行っていた農作業といえば
今のようにコンバインで一気に稲刈りができるわけでもなく、
全て手作業で行う必要があった。それが当たり前だったのです。
収獲したお米も、まず米俵を作るところから始めなければならない。
農業というのは非常に苛酷だったのだ。
生きていくために、「農業」は不可欠であり、
とらえ方によっては「楽」であり「苦」でもある。
そんな農業がここまで進化してきた理由の一つには、
必ず、「先代の農家の方々の努力があった」に違いありません。
それが積み重なって、今、ここまできたのです。
ということで、
更なるレベルアップのため、
昔の農業について学んできなさいと言われ、
たかねざワープした先は、