[ましこ・あ・ら・もーど]2012年10月23日
五十六回目 “峠の釜めし”の器の工場見学・前編 前編の今回は土を練る所から焼き上げるまでの工程を見学させていただきました。
①土(粘土)を練る →“峠の釜めし”の器専用にブランドされた土を 機械で練り上げ棒状の固まりにします。  ②釜の形に形成
→その棒状の土を35個に切り釜の形になった 型に入れて行きます。 1個作るのに5秒とかかりません。 ③1分程乾燥 →型から外しやすい様に少しだけ乾燥させます。 ④バリ取り ⑤一晩乾燥 →窯から出ている熱を使い乾燥させます。 熱は上に上にいく為、バリ取りされた器は工場の天井に ハンガーでぶら下がっておます。 ⑥釉薬かけ →一晩かけて乾燥された器は飴釉を付けます。 飴釉は焼く前はグレーの色をしています。 ⑦本焼き →40mほどのトンネル窯で12時間ほど焼きます。 40mのトンネルは所々温度が違うので、 12時間台車が自動で移動していきます。 1回で1万個が焼きあがります。 という工程になっています。 その工程のほとんどが機械化されていました。 人の手で作られる物とは一味違う工場で作られる益子焼、 見ていてとてもワクワクしました。   現在はほとんどの工程を機械で行い1日7tの土を使い
およそ1万個の器を作っています。 でも今から20年ほど前は全てを手仕事で作っていた為、 近くの窯元さんと共同で作っていたそうです。 プラスチックなどの器と違い保温性の高い益子焼の器、 食べ終わった後のあの器の良い使い道を知っている方 是非、益子styleまで★☆ 後編では、出来上がった器の出荷作業を見学してきた模様をお送りいたします。 引き続きご案内頂くのは株式会社つかもとの関教寿さんです。 後編もお楽しみに♪ |














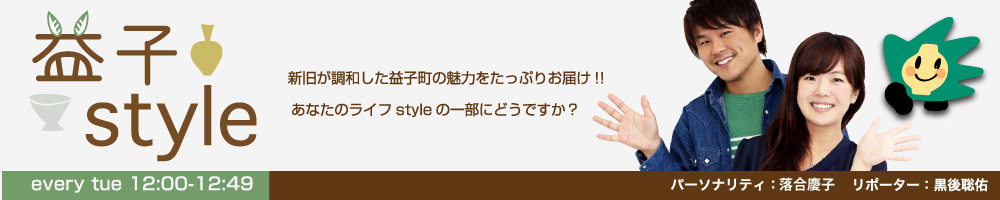
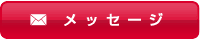
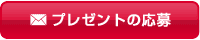
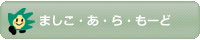
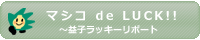
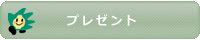
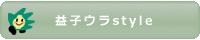
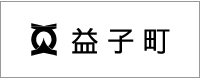
今週と来週は二週に渡りクロスケさんと一緒に、
群馬県横川駅を中心に販売されているおぎのやさんの“峠の釜めし”の器を作っている、
株式会社つかもとの工場を見学しに行ってきた模様をお伝えしました。