[ましこ・あ・ら・もーど]2012年9月11日
五十回目 益子焼を作ろ・知ろう 第5回では1つづつ行った作業を簡単にご紹介します。 まずはクロスケさんが手びねりで作った 自身の顔ほどの大きさのある壷は・・・ クロスケさんたっての希望で 壷の下の部分から黒・黄色・赤・コバルトの“夕焼け”の色にしました。 続いてクロスケさんがろくろで作った多目的に使えるボウルは・・・ 白い釉薬に縁を緑色にしました。 クロスケさんは全て“吹き付け”と言う技法で釉薬付けをしていました。 この技法自分の息を使って釉薬を吹き付ける技法です。 なので息の強さや長さによって出る色が変わってきます。 一方、私は手びねりで作った30㎝ほどある三角柱の花瓶は・・・ △の角の部分のみに黒い釉薬を浸し、 それを3つの角の全て行いました。 続いてろくろで作ったお猪口ととっくりは・・・ 島田先生の作品に良く見られる紫色を使い 1㎝代の水玉模様を筆で書きました。 2人も全く違う技法で作業を行いました。 絵付け・釉薬かけは基本的に1回限りの作業なため緊張しましたが とっても楽しみながら作業が出来ました。 次回はついにこの企画の最終回!!! この絵付け・釉薬かけをした作品を本焼きをした作品とご対面します。 焼いた作品がどの様な色になるのか不安でもありますが楽しみでもあります。 来週の放送をお楽しみに♪ |
前のページ 次のページ














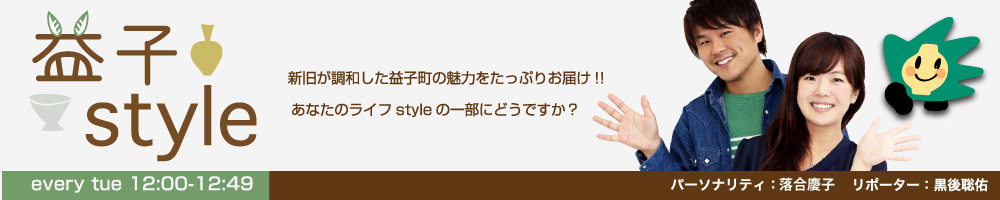
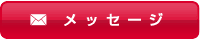
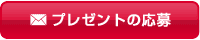
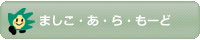
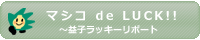
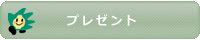
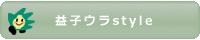
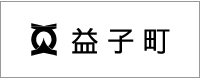
「益子陶~く特別企画 益子焼を知ろう・作ろう」
7月からスタートしたこの特別企画では合計6回に渡って
クロスケさんと一緒に益子焼を土選びの段階から
陶芸作家 島田恭子先生に教えて頂いています。
第5回の今回はろくろ・手びねり2つの手法を使って作った
私たちの作品を素焼き(釉薬などをかけずに窯で焼く事)しまして
それに絵付け・釉薬かけをしました。
まず手びねりの作品は2つとも内側を黒の釉薬で塗り、
外側とろくろの作品は色の付きが良い様に白い釉薬を塗りました。
但し、私の手びねりの作品は赤土の材質を残したい為、
白い釉薬は塗りませんでした。