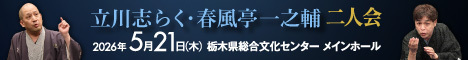[番組情報]2020年9月29日
今週は新田弁護士に「海外向けのEコマース「越境EC」」について伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
 今週は、国際関係の弁護士業務が専門 宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 「海外向けのEコマース「越境EC」」 について、伺いました。 【Eコマース】 電子商取引のこと。 簡単に言うとインターネット上での商品の売買、 つまり、インターネットを介したショッピングです。 日本にいる事業者が、 海外にいる消費者にEコマースで商品を売ることを 「越境EC」といいます。  ●越境ECの注意点
「越境EC」と一言で言っても、 中国、シンガポールなどの特定の国に絞る場合と、 世界中を対象にする場合がありますので、 どちらでいくのか、まず決めていただく必要があります。 これは、どの市場をターゲットに何を売るのかという、 マーケティングの意味でも大事ですが、 それによって、実務も変わってきます。 例えば、決済手段一つとっても、中国なら、中国、 シンガポールならシンガポールで使われている 決済手段を使うべきですし、全世界対象にするなら、 ペイパルなど世界的に有名な決済手段にしたほうが 良いといえます。 また、ローカルモールに出店する場合には 現地法人が必要などという場合もあります。 グローバルモールだと そういう縛りはないことが通常です。 このように、ターゲットを特定の国にするのか、 世界中なのかにより、取るべき手段も変わってきますので、 漠然と越境ECというのではなく、 具体的に考えていただく必要があります。  ●「越境EC」のトラブル防止について 越境ECの場合、 配送のミス・関税のトラブル・商品クレームなど、 トラブルはどうしても多くなりがちですので、 想定される事柄については、 規約で予め定めておく必要があります。 例えば、よくあるトラブルの一つに、 関税の負担があります。 売主としては受取人負担だと思っていたけれど、 買主としては売主負担だと思っていたようなときに トラブルになります。 ですので、受取人負担であれば、受取人負担であると、 規約にはっきり記載しておく必要があります。 なお、特定の国向けの越境ECであれば、 関税の額は予め調べられますので、 料金に含めておくと、 見え方としてはよりよいかもしれません。 いずれにしても、 関税の取り扱いをどうするのかあらかじめ決めて、 記載しておけば、トラブルが防げます。 ●紛争解決の場所・方法・準拠法 先程の話とも少し関係しますが、紛争に備え、 紛争解決の場所・方法と 準拠法を決めておく必要があります。 越境ECの場合には、消費者は外国にいるわけなので、 何か揉め事になった場合に、 どこの法律に基づいて契約を解釈するのか、 裁判とか仲裁は、 どこでどうやるのかという問題が必ず出てきます。 ですので、例えば、準拠法は日本法、 裁判管轄は東京地裁などと 規約で決めておく必要があります。 ただ、ここで少し難しいのは、 仮にこういう規定があったとしても、 実際は機能しないことがあるということです。 というのは、 事業者と消費者との間の取引に関する紛争については、 消費者の住所地の裁判所に管轄がある。と、 定めている国が少なくないので、利用規約等で、 日本の裁判所が専属的管轄を有する。 という規定を置いている場合であっても、 国外の消費者が日本の事業者を自国の裁判所で訴えた場合は そこで裁判ができてしまう可能性があります。 準拠法についても同じで、 消費者の国の法律が準拠法になると定めている国もあるので、 その場合には、いくら規定で日本法と定めても、 消費者の国の法律が適用になる可能性があります。 ●越境ECについての情報サイト 中小機構が 「中小企業のためのEC活用支援ポータルサイト」 というものを作っています。 ECに関するYOUTUBEのビデオをたくさん配信しているので、 とても分かりやすいです。 どうやって中国のモールに進出するかとか、 各国のEC市場についてとか、 中小企業にとって分かりやすい説明がたくさんあるので、 越境ECに興味のある方は 身近なところから学び始めると よいのではないかと思います。 また、ジェトロも 「ジャパンモール」というものをやっていて、 自社の商品を日本国内で買いとり、 自社に代わって海外のECサイトに 出品してくれるようなサービスなので、 輸出の手間がなく初心者でも始めやすいと思います。 今日ご紹介した情報は 栃木から世界へジャンプのYoutubeチャンネルも ご覧ください。 |