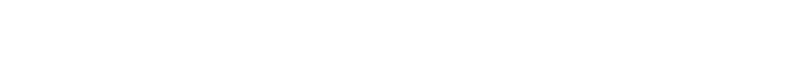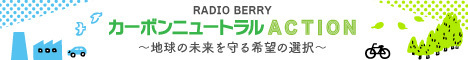[番組情報]2020年11月24日
今週は新田弁護士に「インコタームズ」について伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
 今週は、国際関係の弁護士業務が専門の
宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 「インコタームズ」 について、伺いました。  ●インコタームズとは
①いつ・どこで売主が買主に物品を引き渡すのかということ。 ②売主と買主のどちらが運送費用を負担するのか。を、 決めるルールです。 国内取引の場合、例えば 栃木の会社が、大阪の会社に商品を売るとしたら、 大阪の会社に商品を引き渡すのが普通です。 では、国際取引の場合はどうなのでしょうか。 ●国際取引の場合
必ずしも、そうだというわけではなく、 他にもいろいろなバリエーションがあります。 例)栃木→シンガポールだとします。 栃木からシンガポールまで遠いので、 途中に、引渡しに使えるポイントが色々あります。 例えば、実務上よく使うのは、 栃木から横浜まで商品を運んで、 横浜の港で引き渡すというパターンです。 横浜の港で、シンガポールの買主が手配した運送人に 商品を託した時に、引き渡し完了になります。 もちろん、商品はこの後も、横浜の港から シンガポールの港まで船で運ばれていくのですが、 引渡は横浜の港で完了するということになります。 売主である栃木の会社が運送料を負担するのも、 横浜の港までです。 〇他の一例 他に工場渡しといいますが、 栃木の工場で引渡しが完了してしまうパターンもあります。 シンガポールの会社が手配したトラックなどが 栃木の工場に来て、商品を持っていくイメージです。 この場合、栃木の工場で引渡しが完了になります。 運送料は全て買主が負担することになります。 □どのパターンを選ぶかで、
手間も違いますし、商品の価格も違ってきます。 つまり、栃木の会社まで取りに来てもらえるのであれば、 栃木の会社は運送料の負担がないので、 商品の価格は運送料や関税などが 含まれていない価格になります。 逆に、シンガポールまで運ばなければならない条件だとすると、 栃木の会社としては純粋な商品価格に 運送料や関税などを上乗せして 商品価格を設定する必要があります。 どのパターンを選ぶかで、 商品価格は何倍も違ってきたります。 □様々なパターン・ルールの取り決めがインコタームズ。 インコタームズのルールは、FOB、EXWなど、 アルファベット3文字で書かれています。 先ほどの工場渡しはEXWという3文字ですので、 契約書ではEXWと記載します。 インコタームズは貿易商人の間の共通言語ですから、 相手がどこの国の企業であっても、EXWといっただけで、 商品がどこで引き渡されるのか、 誰がどこまでの運送料を負担するのか、 すぐに分かり便利です。 ●インコタームズを利用する上での注意点。 インコタームズは国際商業会議所が作った国際的な規則で、 法律ではないので、当然に適用されることはありません。 インコタームズを使いたければ、 契約でそのように記載する必要があります。 法律のように自然に適用されるものではないことは 覚えておいてください。 |
|
2020年11月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~  今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に 「入管に関する最新情報」 について、お話を伺います。  新型コロナウイルスの影響により、 ヨーロッパでは第二波の感染拡大が懸念されています。 そのため、ロックダウンされる地区も出てきました。 ロックダウンとなると、 日本からヨーロッパへ、 ヨーロッパ在住者が日本へ。の、 海外渡航は非常に難しくなるため、 必要な国際交流・ビジネスのやりとりがある方は 情報をしっかり確認しておくことが大切です。 また、仕事等の理由により、 ヨーロッパから帰国。という場合には 必要な手続き・検査ののち可能です。 帰国後、日本での必要な措置は、必要である場合、 必要でない場合がありますので、 海外渡航の内容で、どちらに当てはまるのをか、 外務省等のホームページで、 最新の情報を確認するようにしておきましょう。 現在の状況では、短期滞在の在留資格では、 日本に来日することは出来ません。 ただ、日本に移住・住まいを移すという場合に限り、 必要な条件を満たしたうえで 「在留資格認定証明書」が発行されれば、 ビザを受け取って、日本に来ることができます。 そのため、数週間~数か月の短期間の滞在も出来ません。 そんな中、一部緩和が始まろうとしているのが、 「ビジネスに基づく短期滞在」です。 これは、東アジア中心の国々の間で、 数日間の超短期滞在は緩和を認める。 という動きがあるためです。 ただ、その間ならどの国でも緩和されるのかというと そうではありませんので、 該当する国、期間、目的、範囲、など 外務省のホームページに詳しいことが記載されていますので 必要であれば情報を知っておきましょう。 これらの情報は、日々更新されていきます。 数週間~1か月前の情報では 古くなってしまうことが予想されますので 随時、情報をアップデートしましょう。 入管に関する新型コロナウイルスによる影響と 最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、 「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで ご連絡ください。 |
|
2020年11月10日
今週も引継ぎ、株式会社 北研 営業部 石塚 誠さんへのインタビュー!~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~  今週も引き続き、 株式会社 北研 営業部 石塚 誠 さん に お話を伺いました。 栃木県壬生町に本社を構える株式会社 北研は 「きのこの総合メーカー」。 研究開発、種菌、資材・プラント、 きのこ生産・販売を行っている会社です。  先週は、北研が 海外展開を見据えているというお話を伺いました。 東日本大震災の以前では、 情報番組でも取り上げられた海外輸出事業で 香港へ高級シイタケを輸出していましたが、 原発事故の影響で輸出が出来なくなってしまったので、 今回は不屈の精神でリベンジするべく 気合が入っているそうです。 以前は中国への営業も行っていた石塚さん。 昨年は1か月のうち半分程、中国に出向いていましたが 現在は渡航ができません。 シイタケの生産量世界一を誇る中国は 工場の敷地の端がかすんで見えるくらいの 広大な敷地で栽培しているそうです。 最近まで中国では、 品種登録による育成者権を守、る法整備が整っておらず 無断で登録品種をコピーされても、 損害賠償請求ができないため。 北研のように投資をして品種開発をする 一般企業がありませんでした。 その中で、中国企業は、 日本のキノコ種菌メーカーが 優良品種を多数所有していることを知っているので 素晴らしい品種・技術をもっているのではと、 北研も営業活動を通じて期待を感じているようです。  シイタケの品種を 無断でコピーして使用することが当たり前だった中国では、 正しい管理がされず、品種の変異が起きてしまい 栽培が安定しない企業が多い傾向にありました。 そのため、品種が管理されたものを購入することで、 経営を安定させ、対価を支払っても、 メリットがあることを理解するのに時間がかかること。 に加え、 自然栽培・自然の環境を利用した栽培がほとんどのため、 地域の気候や風土にあった、 品種や技術が変わってくるためその見極めが難しい。 と、石塚さんは言います。 一方、北研では、 キノコ生産のコンサルティングも行っています。 「栽培技術コンサルティング」は シイタケ栽培をしている企業に対して、 シイタケ品種を使用した栽培種菌や菌床の製造、 および、栽培技術をコンサルティング。 また、シイタケ栽培に新規参入する企業へ 施設設計のコンサルティングや 研究施設への品種技術コンサルティングを行っています。  ■株式会社 北研今後の目標・展望について。 まず、今後3年間は縮小傾向にある、 国内事業を死守しながら、 キノコ生産量世界一の中国、 シイタケ消費量が多い台湾事業に注力した、 海外事業を足掛かりとし、消費拡大中の 東南アジア・欧米にも展開したいと思っています。 10年後に国内外の売り上げ50億円を目標にしています。 それでは最後に、 石塚誠 さんに世界への扉の鍵を開いていただきます。 世界に通用するものづくりにおいて、 最も大切なことは何でしょうか? 各国の顧客ニーズに対応する 技術・品種の開発はもちろんですが、 それらを組み合わせたシステム提案を継続的に行うことで 企業経営をサポートし続けることが出来ることが 重量だと考えています。 単に品種や技術の切り売りではなく、 私たちは キノコのグローバル総合メーカーを目指しています。 また少し、世界への扉が開いたような気がします…  |
|
2020年11月3日
今週は、株式会社 北研 営業部 石塚 誠さんへのインタビュー!~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~  今週は 株式会社 北研 営業部 石塚 誠 さん に お話を伺いました。 栃木県壬生町に本社を構える株式会社 北研は 「きのこの総合メーカー」。 研究開発、種菌、資材・プラント、 きのこ生産・販売を行っている会社です。  今回は種菌工場の中に、 お邪魔させていただきました! この時は、 種菌の培地用の栄養体を混ぜる作業の最中でした。 北研は昭和36年に壬生町で前身となる会社を創業。 なめこの生産技術を確立して栽培用種菌を販売。 当時は「なめこの北研」と言われていたそうです。 昭和63年に北研600号という 臨床シイタケ栽培用品種と、特許技術を開発。 普及が始まると、主力事業が 菌床しいたけ栽培用種菌と、栽培敷材となり、 今では全国およそ2000件の農家・シイタケ工場が 使っているんです。  北研は、自然の環境を利用して 設備投資を抑えたビニールハウスでの自然栽培、 断熱効果の高い建物での空調栽培など、 栽培方法に合わせた品種を取り揃えてもいます。 また、直径10cm以上の大型シイタケを栽培できる品種や しいたけが発生しない30°以上の環境でも栽培できる品種など、 ニーズに合わせて開発して品種もあります。 現在は国内に流通する生しいたけの、およそ50%の生産者が 北研の種菌で生産しているほどのシェア率を誇ります。 主力の菌床シイタケだけでなく、新種の開発にも力を入れ、 きくらげ・ヒラタケ・マイタケ種菌の販売、 そして、エノキ茸やエリンギの品種開発にも力をいれます。  今後は海外への展開にも目を向けている北研。 現在の日本のキノコの生産量は年間47万t 世界では5千万tにもなるそうです。 世界的な健康志向により、消費量は拡大傾向、 さらに、シイタケは各国での中華街消費や 日本食ブームの広がりもあり、 欧米のスーパーでも店頭にも並ぶ商品なんだとか。 アジア圏でみると、中国は、 年間3千600万tで世界一のシイタケ生産量を誇ります。 これは日本の生産量の140倍以上の数字。 しかも、価格は日本の7分の1ほど。 日本の価格で販売することは難しいため、 海外展開には中国に合わせた、 ビジネスモデルの構築が必要になります。 ですが、市場は日本に比べてはるかに大きいため 海外展開には期待が持てる。と、石塚さんは話します。 また、来週もお話を伺います。 |