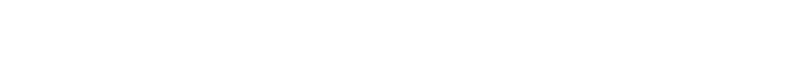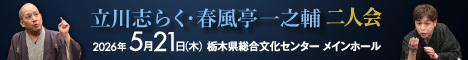[番組情報]2021年3月23日
今週は新田弁護士に「契約」について伺いました。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
 今週は、国際関係の弁護士業務が専門の
宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 貿易に関する重要ポイントのうち、 「契約」 について、伺いました。  ●契約書の締結
企業から 貿易に使う契約書を作成して下さい、という依頼は とても多いです。 今の時代は、国内取引でも国際取引でも、 取引する時には契約書を作るというのが スタンダードになっていますので、 もし、契約書なく取引しているかも、 と思い当たる節がある方は、 この機会に弁護士に相談していただいた方がよいです。 ●契約書の種類 どういう契約書を締結するかは、 どのような取引をするかによります。 県内の企業でご依頼が多いのでは、 いわゆる「売買基本契約書」「販売店契約書」の2種類です。 ○「売買基本契約書」とは、 物の売り買いに関する契約書です。 何をいくらで売るのか、届いたもの に不具合があったらどうするか、というような、 売買に関するルールを決めます。 例えば、 県内の企業Aがアメリカの自動車メーカーBに、 車の部品を販売し、 アメリカの自動車メーカーBはその部品を買って、 車を作るというような場合に、この契約書を作ります。 ○「販売店契約書」とは、 外国のパートナーに商品の販売店になってもらう契約です。 例えば、 県内企業Aが、自社のお菓子を、中国の企業Bに販売し、 中国企業Bは、仕入れたそのお菓子を 中国国内で売っていくというような場合です。 この場合は、この中国での販売権は独占権なのか、 非独占権なのか、を決めます。 独占権だとすると、県内企業Aとしては、 この中国企業B以外に、中国国内に販売店はもてないので、 この中国企業Bがたくさん商品を買って、 たくさん商品を中国で売ってくれないと困るので、 年間の最低購入量を定めたりします。 テリトリーと言って、 Bはどこの範囲でそのお菓子を売っていいのか、 中国国内といっても、 本土だけか、香港、マカオ、台湾なども入るのか、 ベトナムのお客さんから、この中国の会社に、 お菓子を買いたいと引き合いが来たらどうするか、 などをきめます。 また、中国国内でそのお菓子を売る際には、 当然県内の企業Aの名前や、ロゴを使って 宣伝していくことになるので、 その商標の使用の仕方などを決めます。 ●契約書の作成について 契約書は英語で作ることがほとんどです。 相手が中国であろうがベトナムであろうが、 ビジネスの世界では英語が共通語なので、 英語で作ることが多いです。 自社としての契約書の雛形をつくっておきたい。 というご依頼も多いのですが、 やはり英語で作ります。 英語で雛形をつくっておけば、色々な国相手につかえるので、 県内の企業としても一番使い勝手がよいと思います。 ●日本語の契約書との違いは? 形式的なことでいうと、英語の契約書の方が 日本語の契約書よりも長いことが多いです。 先程の売買基本契約書だと、だいたい15-20ページくらい、 販売店契約書だと、20-25ページくらいでしょうか。 あとは印鑑を押すのではなくサインをします。 内容的にも、重複する部分もありますが、 やはり違いもあります。 分かりやすい例としては、 国内取引だと、 契約書は日本法で解釈することが当然なので、 準拠法が日本法とは明記しないことも多いですが、 国際取引の場合には、 何法でこの契約書を解釈するのか必ず書きます。 ですので、手元にある日本語の契約書を翻訳して、 英語にすれば、 それで国際取引にも伝える契約書になる。 というわけではありません。 やはりこれはこれで独自に準備する必要があります。 ●契約書の作成依頼 インターネットで似たような契約書を探して、 それを使う、というのは危険です。 契約書というのは具体的な取引に合わせて作るものです。 自分が売主なのか買主なのかによっても、 有利な契約内容というのは全く変わってきます。 特に、現在はコロナ禍で色々な特殊事情がありますので、 それを加味して契約書を作る必要があります。 最近多いのは、現在海外渡航することができないので、 商品の使い方に関するトレーニングをオンラインで行う、 商品を海外発送する前の事前検査をオンラインで行う。 などの条項です。 私も、会社の具体的ニーズをお聞きしながら、 今までは作ったことがなかったような条項を たくさん作っています。 |