[特別番組"SDGs CONNECT"]2021年12月5日
特別番組「SDGs CONNECT」 2021年12月5日放送 日光アカデミーは、日本両棲類研究所の運営を中心に種の保存や発生・再生学をおこなっています。
体性幹細胞(細胞)を世界で初めて発見、ヒトへの世界初となる幹細胞移植を行い、 更に日本初となる、再生医療の厚生労働省の評価基準を作るなど、 再生医療の先駆けをされた現所長さんの下 発生学、再生学の研究を通じて、現存する全ての生物の中で、最も遺伝子を作るD N A総量が多い 日本固有種のアカハライモリの再生能力を最大限に生かした再生医療、 ベトナムビンメック病院との提携で全脳性小児麻痺8歳の女子の骨髄から イモリの再生プロセスを利用して脳細胞を作成、移植し 世界初めて全脳性小児麻痺が自力で歩行させる事に成功! こうした研究の成果を広く応用し、また、飼育、調査から得たノウハウを用いてコンサルティング事業を展開、 自然環境調査、環境アセスメント、セミナーの開催を積極的に展開しています。 SDGsへの取り組みについては1970年代に、初代所長による自然保護活動、 並びに種の保存とその計奴のために 世界でも最先端のフィールドミュージアムとして設立されたところからスタート。 持続可能な開発のための自然保護を提唱し、多くの大規模開発の指導を行うと同時に、 再生医療研究を通じて、不治の病を治療可能にし 今後の社会に貢献するという目的で活動を活発化しています! また、物理学者でもある所長さんの発展の概念として、 経済は生態から資源やエネルギーを採取し、そして生態系へ生産物、CO2、ゴミを排出する。 環境問題において重要なのは、エントロピーを増加させない努力を行う事である。 排出物の処分が出来なくなった時点、すなわちエントロピーが最大となったところで、 経済成長は止まらざるを得なくなることを理解すること。 地球という限定された空間でのエントロピーの増加を最小化する事が環境保護になる。 と言うものです。 日光アカデミーでは、企業や自治体におけるESFへのコンサルティングを行い 熱力学として、エントロピーの概念としてESGを捉えるための支援を行う事で、 真のSDGsに向けた健全な環境保全を支援しています。 2組目は… クリーニングのフジドライでおなじみ 洗濯の原理を見直し、常に高いクオリティを追求する「フジドライ洗濯研究所」  創業100年以上の歴史あるクリーニング屋さん。
すでに持続可能経営をされていますが、 「クリーニング(洗濯)」=「排水汚染」という印象をお持ちの方も まだいらっしゃるそうです。 フジドライ洗濯研究所では、100年以上続くプロの洗濯を提供しながら、 自社敷地内にて、工場からの排水は敷地内清浄水槽で、金魚が飼えるレベルまで清浄処理し排出しています。 また、ハンガーリサイクルを積極的に行い、できるかぎり再利用(リユース)を行っており かつ、再利用できないハンガーは、産業廃棄物として処分するのではなく、 PPリサイクルのために専門リサイクル業者と提携し100%リサイクル! もちろん、工場で使用する薬剤等の成分内容に細心の注意を払い、蛍光増白剤や環境ホルモン(内分泌かく乱物質)は使用していないのです! さらに最近では、学生服のリユース事業にも積極的に取り組んでおり 卒業して着なくなった学生服を、次の世代の地元学生さんが着られる仕組みを形成。 そして、お洗濯サブスク! 「ポンポンランドリー」も順次展開スタート! 洗って・干して・こんだり・たたんだり…毎日のお洗濯にあなたは何時間費やしていますか? ポンポンランドリーは、定額でプロのお洗濯を何度でも利用できます! 実はこれ、一般家庭での洗濯で使う 1/6 の水量しか使ってないんです! もちろんプロの洗濯だから、ふわふわ仕上がりに! 私たちの暮らしが、どれだけ地球に負荷をかけているか? 地球のことを考えたら、こっちの方が正解かも |
|
2021年11月7日
特別番組「SDGs CONNECT」 2021年11月7日放送毎月、第一日曜日の夜7時からお送りする特別番組「RADIOBERRY SDGsコネクト」!
毎回、SDGsを支える取り組みをする企業からお二人のゲストをお迎えして 栃木のSDGsについて語り合います! 今回は…小山市に本社を構える ペットボトルリサイクル・再生樹脂販売を行う「協栄産業 株式会社」 から 代表取締役社長の古澤栄一さんにお話しを伺いました!  醤油の瓶から始まったペットボトル。 移動コスト、衛生面、破損などのリスクから、ガラス瓶に代わり 飲料水ボトルとなって私たちの身近な存在になったペットボトル。 古澤社長は、会社設立当初から「どうにか再利用できないか?」と考えていたそうです。 当時は、回収したペットボトルを、卵パックや洋服などの生地に作り替えていましたが、 どれも1WAY…ペットボトル→リサイクル品で、 結局一度しか生まれ変わることができません。 ペットボトルをペットボトルとして再利用することが一番と考えていた古澤社長。 もちろん世の中には、リサイクルペットボトルはありました。 しかし、それらの多くは石油からのヴァージンオイルに、リサイクル素材が 30%入っているものばかり。 結局、次から次へと石油が使われます。 また、飲料メーカー(市民の声)としては、 「一度使用したモノを使うのは、衛生面でどうなのか?」と なかなか受け入れられなかったそうです。 さらにペットボトルの素材は、熱を加えるたびに劣化してしまいます… 何度もこれらの問題に挑み、ついに世界初! リサイクルペットボトル100%使用(ヴァージンオイル不使用)で 劣化もなく、衛生面も、生まれたてのペットボトルと同じモノを作り上げる技術の開発に成功しました。 さらには、リサイクルの工程を従来の半分でできるシステムも完成! これで大幅にCO2の削減ができるようになり、かつては考えられなかった 新しい時代が始まろうとしています。  放送では、TOKYO2020大会で、MISIAさんが国歌斉唱の際に来ていたドレス
サッカーの名門、レアルマドリードのジャージや、ユニクロ、錦織圭選手のテニスウェアも 協栄産業の技術が採用されているなど、世界をリードする貴重なお話も聞くことができました! ※2022年開催「いちご一会とちぎ国体」の栃木県代表ジャージは、県内で回収されたペットボトルから作られます。 ※古澤社長にフォーカスした映像もぜひご覧ください  そして後半は…
上岡裕さんと…「スポーツとSDGs」について 秋…おいしいものがたくさんありすぎて、ついつい食べ過ぎてませんか? コロナ自粛もあり、運動不足ぎみの方も? …でも、やらされるのは嫌! 音楽を聴きながら35分、カラダを動かすだけで 運動不足の解消にもなるし、 なんと「知症予防」が期待されると研究の結果も発表されているんだそうです! これは、カラオケなどで思い出の曲を歌うだけでも違うそうで 楽しく、カラダにも良い、健康的な生活を送ることができるので ぜひ(少し歩くだけでも)今日から…とは言いませんが 明日から試してみて下さいね! ※くれぐれも陽が落ちてからや夜間の外出、運動には十分に気を付けて下さいね! |
|
2021年10月3日
特別番組「SDGs CONNECT」 2021年10月3日放送毎月、第一日曜日の夜7時からお送りする特別番組「RADIOBERRY SDGsコネクト」!
毎回、SDGsを支える取り組みをする企業からお二人のゲストをお迎えして 栃木のSDGsについて語り合います! 今回は… 企業のSDGsへの取り組みを応援する 「栃木県産業労働観光部 産業政策課」の 中里由佳さんと落合茜さんにお話し伺いました!  栃木県産業労働観光部は、
「新しい工場を立てたい!」「フード事業を始めたい!」などといった 県内の産業・労働・観光の窓口業務 また、次世代産業と言われる「AI」や「IOT」関連などを県内に広げていきましょうという新しい取り組みも行っています。 その中で…「栃木SDGs推進企業登録制度」を立ち上げ、 県内企業や事業者のみなさんに幅広くSDGsを呼びかけています。 2019年度に実施した調査によると 県内企業のSDGsの認知度は約30%という結果でした。 しかし、実際には各企業内で「労働時間を守ります」「ハラスメント対策をしています」など すでに取り組んでいることもわかりました。 「SDGsと今やっている取り組みがどう結びつくかがわからない…」 これを受け、まずはチェックリストの作成など、それらを結びつけるお手伝いをしているそうです。 お二人とも、もともとSDGsに詳し詳しくはなかったそうですが この制度立ち上げと共に、みなさんと一緒に学んでいます。 立ち上げ当時は、「まずSDGsって何?」という声が多かったそうですが 説明会や会合などを開き、順調に登録企業も増え この1年間で254社905事業所が登録。 多くの方がSDGsに興味があるということがわかりますね! 今後は、初期に制作したチェックリストを、「今どうなのか?」見直していく呼びかけも行っていきます。 未来を考える一つのきっかけとして 企業や事業者さんだけでなく、県民みんなで手を取り合って 壮大な未来ではなく、まずは3年後の近い未来を考える… これを機に、それぞれのビジョンが見えてきそうですね!  マダガスカルでは古くから「焼き畑農業」が行われ、
森が水田や畑、牛を育てる草地などに置き換えられてきました。 また、調理用に活用する薪や炭などの燃料としてどんどん木が伐採されています。 その結果、現在の森林面積は10%以下となり、 生物多様性の喪失、野生生物の生活圏の減少、土壌流出、砂漠化などが危惧されています。 マダガスカルの国道を行くと、遠くからは緑に見える山々ですが、 近づいてみると木が見当たりません。 木が失われた山々では、山崩れがあちこちで起き 小さな集落や農地に迫り、多くの被害も出ています。 住民には森に対する教育が行われておらず、適切に森を管理することができていません。 それを改善するためにもSDGsの4番目のゴールに掲げられる 「質の高い教育の普及」が不可欠です。 マダガスカルの主要メディアである『ラジオ』を通し 森の大切さや日本の文化を伝える クラウドファンディングに参加してみませんか? |
|
2021年9月5日
特別番組「SDGs CONNECT」 2021年9月5日放送毎月、第一日曜日の夜7時からお送りする特別番組「RADIOBERRY SDGsコネクト」!
毎回、SDGsを支える取り組みをする企業からお二人のゲストをお迎えして 栃木のSDGsについて語り合います! 今回は… 小山市にある廃棄物の処理や運搬、そして清掃事業を行う 「有限会社 関東実行センター」が取り組むSDGsについて 取締役の山本久一さんに、いろいろとお話し伺いました!  ●「有限会社 関東実行センター」 一般/産業廃棄物の収集運搬、下水道の維持管理、土木建設業、道路の清掃業、 さらには飲み水の貯水槽などの清掃…と 私たちの生活に密着、支えてくれている企業。 まちのみんなにだけでなく、 自社社員の健康も大切に考えた健康経営にもチカラを入れているようです。 そんな山本取締役のSDGsの取り組みを通じて気になっていることとは…? 多種多様のゴール(目標達成)があるSDGs、 一つの企業で抱え込まず、まずは得意分野から! やがてそれぞれの分野の企業とつながって(パートナーシップ)いければ… みんなでゴールに向かってアクションしましょ♪ どうぞ引き続き、インターンシップなど若い世代の方たちと一緒に SDGsについて考え、アクション(実行)していってくださいね!  そして後半は…この番組のSPアドバイザー・上岡裕さんについて ●「特定非営利活動法人 エコロジーオンライン」 地球環境問題の解決のための「情報・知識の共有」を通し それぞれ受け取った方々のライフスタイルを エコロジカルに変えるためのお手伝いやアドバイスを行っています。 そもそも上岡さんが「エコロジーオンライン」を始めた(設立した)きっかけは何だったのか? かつて「SONYミュージック時代」に目の当たりにした海外での体験と ふるさと栃木県で発生した日本初の公害事件に立ち向かった田中正造さんに感化され まさかの行動に? 音楽業界人ならではの、エコや各時代の社会情勢を揶揄した 様々な名曲につて、これからもSDGsと一緒に教えてください♪ |
特別番組「SDGs CONNECT」 2021年8月1日放送毎月、第一日曜日の夜7時からお送りする特別番組「RADIOBERRY SDGsコネクト」!
毎回、SDGsを支える取り組みをする企業からお二人のゲストをお迎えして 栃木のSDGsについて語り合います! 今回は… 佐野市に本社を置く、無機材料素材メーカーの「吉澤石灰工業株式会社」 と、 地域の良好な水環境の維持管理を行う「一般社団法人 栃木県浄化槽協会」 から お客様をお迎えしました♪  ●「吉澤石灰工業株式会社」
創業1873年(明治6年) ドロマイトや石灰石を採掘加工している吉澤石灰工業。 石灰業界でSDGsに取り組んでいる企業メーカーは、国内ではまだ少ないという現状から 吉澤石灰工業がまずやってみよう!と取り組み始めました。 まずはSDGsについての考えを共通化させるため、全社員でSDGsの講習を受講。 17の目標を論理的に6つに分けて(CO2対策やイノベーション、ジェンダー、地域貢献など) それらのスペシャリストを社員から作るという、社員全員の当事者意識を育んでいます。 上が目標を作っても下が実行できない… 「カタチだけ作っても意味がない」「自分で作って自分で守るようにしたい」 という社長の考えが印象的でした。  ●「一般社団法人 栃木県浄化槽協会」
栃木県内12の支部で、浄化槽の「法定検査」や 浄化槽に携わるみなさんの「資質向上と正しい知識の普及」を行っています。 家庭から出る汚れた水(トイレ、お風呂、キッチンなどからでる排水)をキレイにする浄化槽。 新築や拡張、リノベーションした際の浄化槽の設置検査は100%であるのに対し、 浄化槽がちゃんと機能しているか?を確認する、毎年の定期検査(水質検査)は73.5%。 約4万基の浄化槽が、ちゃんと機能しているのか?わかっていません。 車に車検があるように、浄化槽も毎年の検査が法律で義務付けられています。 水がキレイになるためには、浄化槽のきちんとした維持管理が必要です。 暮らしの中で、知らず知らずのうちに出してしまうよう排水(車でいう排気ガスのようなもの)を 回収(吸収)する技術が、我々の暮らしを支えている とても大切なSDGsの項目。 汚れた水を流さない→「水の保全(安全な水の確保)」 それが→「海の豊かさを守り」、それらが→「すべての人の健康が確保される」とつながっています。 行政から通知が来たら必ず定期点検を受けて下さい。 それが私たちができるSDGsの一つです。 ※浄化槽の定期検査は、法律で義務付けられている必ずしなくちゃいけないものです! |
前のページ 次のページ















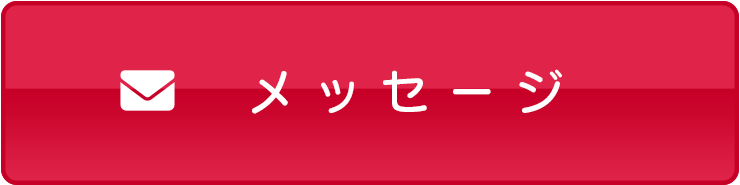


毎回、SDGsを支える取り組みをする企業からお二人のゲストをお迎えして
栃木のSDGsについて語り合います!
一組目は…日光市にある、
生物の飼育や保護の状況を見て、学生に体感してもらう 生命倫理学を提供する
「日光アカデミー 日本両棲類研究所」