[番組で紹介した情報]2025年4月11日
『イヤイヤ期って なんなの? 』 |
|
2025年4月4日
『新学期の 変化とストレス!』この春 お子さんが 入学・進級されるご家庭では、
様々な準備に 慌ただしい日々…、 そして お子さんも きっと、大きな環境の変化に 「期待」と「不安」でイッパイではないでしょうか? そして、そうした 期待と不安、環境の変化は、同時に、 大きな「ストレス」を生み出します。。。 今日は、そんな“新学期の変化とストレス”について ちょっと考えてみましょう。 ::: もちろん、新しいステージへ向かうのは おめでたいことですし、お子さん本人もうれしく感じる子が 多いと思います。そして そんなお子さんは 新しい環境に適応しようと、頑張ります! 入学式や 始業式が 終わってしばらくは 緊張感と気持ちの高ぶりで、ある程度の頑張りがきくのですが、 少し慣れてきた頃…5月の連休明けくらいに ふと緊張が切れて、どっと疲れが出てしまうことが あるんですね。。。 では、そうした疲れをやわらげるために、 周囲の大人たちはこうした「変化」を どのような心構えで 迎えればよいのでしょうか。 ::: まずは 大前提として、 『変化はストレスだ』と 意識しておくことです。 今まで 当たり前だった環境… 生活リズムや 通学路、 制服や持ち物、担任の先生など人間関係が 変わることは、 お子さんにとって かなりの負担です。 でも、そうした変化は避けようとするよりも、あらかじめ 『変化はストレス。対処できる!』と意識しておくだけで、 ちょっと気が楽になるかも知れません。 そして『不安や心配を抱くことは 自然なこと』と 受け入れましょう。お子さんは、周りの人から 「入学・進級おめでとう!」とお祝いされて 「ポジティブな気持ちで頑張らなくちゃ!」と思ったり 本来感じている寂しさや不安を隠してしまうかも知れません。 でも、「新しい環境に入る時 不安や心配を抱くことは自然なこと」ととらえて、 お子さんにも それを伝えてあげると、お子さんも ちょっとリラックスして“頑張りすぎ”を防ぐことができます。 ::: また、とくに新年度の 前後は、 お子さんの様子を“普段の2割増し”くらいで よく観察してみましょう。 いつもとは違うストレスのサインを感じたり お子さんがポロッと 不安を口にしたら…、 「クラス替えが心配?」と声をかけたり、 「小学校ってどんなところだろうね。お勉強 難しいのかなぁ?」 など、お子さんが感じていそうなことを言葉にしてみます。 するとお子さんは、「自分の気持ちをわかってもらえた」と 安心して、ストレスに立ち向かう勇気が湧いてくるかも知れません♪ ::: 大人ができることは、お子さんの変化に気付き、 そのストレスが和らぐよう サポートをしてあげること。 様々に降りかかる、不安やプレッシャーも ぜひ 親子で一緒に、乗り越えていきましょう☆ |
|
2025年3月28日
『新聞の切り抜きで 学力アップ?』皆さんのお家では、新聞はとっていますか?
今は デジタルで購読している、あるいは とっていない、 というご家庭も多いと思いますが、 あらゆるものが デジタル化された現代でも、リアルな 新聞記事を 切り抜いて・スクラップブックを作ることは、 お子さんの 学力アップに 効果的なのだそうです! ::: 新聞の切り抜き・スクラップが どうして 学力につながるのか、 それには大きく3つの理由があるそうです。 ::: 一つは、「読み取る力がつく」。 新聞の切り抜き作業では、たくさんの記事に触れます。 見出しや写真から 記事の概要を把握し、 文章から書き手の意図を読み取ること…、 知らない言葉があっても、前後の文脈から その意味を想像したり、辞書で調べたりすれば、 知識やボキャブラリーが 蓄積されていきます。 ::: そして、「書く力がつく」。 スクラップをまとめる時、記事の要点を短くまとめて メモしたり、自分の意見や感想を書き出せば、 「考えて・書く力」がつきます。 ::: 最後に、「情報をあつめて、整理する力がつく」。 スクラップする 記事を選ぶときには、 “情報を吟味し・選択する”という、じつはかなり高度な 作業が行なわれています。 「どの記事がいいかな~」と考えながら 探す経験によって 情報を収集する力が磨かれ、また、切り取った記事が バラバラにならないように 新聞の名前や日付をメモしたり、 ノートや台紙に貼って 保存する作業では、 情報を整理するスキルも、自然と身についていきます。 ::: …ということで、この、「読みとる力」、 「書く力」、「情報を集めて 整理する力」が、 幅広い学習効果につながることは…、 何となく 想像がつきますよね! 日本新聞協会の 2019年度の調査によると、 新聞のスクラップを週に1回以上 行なっていた小学校では、 全国学力テストの正答率が、国語・算数ともに 平均を上回っていたそうです! ::: 新聞の切り抜きは、新聞、ハサミ、ノート、のり、 筆記具などがあれば、小学校低学年からでも、 気軽に始めることができます。 複雑な文章が 読めないうちは、写真つきの易しい記事から お子さんの 興味のわくものを 選んで。 それをノートに貼って、余白には 新聞の名前と 発行日、 記事に対する感想や 自分の考えなどを 書き込めば OKです☆ ::: さすがに 毎日は 難しいかも知れませんが…、 先ほど紹介した 新聞協会の調査のように、週に1回でも、 チャレンジしてみる価値はありそうですよね♪ また、記事のスクラップは、お子さんが 普段から どんな事に興味をもっているかを 知る、 よい機会にも なると思います。時には 親子で新聞を広げて、 楽しくスクラップしながら、アレコレ、 語らってみては いかがでしょうか。 |
|
2025年3月21日
『レジリエンスの育て方!』レジリエンス… それは、心の弾力性や 回復力、
凹んだところから 立ち直るチカラ、のことです。 …変化が激しく、先行き不透明な 現代では、 さまざまな逆境や 困難にも 負けない 心を育てる、 「レジリエンス教育」というものが、注目されています。 ::: そう聞くと、難しく感じるかも知れませんが、 レジリエンス教育の基本は、怒りや悲しみ、イライラなど ネガティブな感情を 否定せずに「認めること」。 日々の 子ども達への声かけで、 それを表現していく、ということです。 ::: 具体的には、例えば…、お子さんが、 『友達からイヤなことを言われた』と言って 泣いて帰ってきたとき。 「大したことないよ!気にしなくていいよ!」 …と 言いたくなりますが、実は、これでは、 お子さんの 心のモヤモヤは解消されず なかなか回復に つながりません。 そこで、レジリエンスを育てる声かけは… 「そっか、それはイヤな思いをしたね。」と 寄り添う言葉をかけること。 こんなふうに、親に“共感”してもらえると、 それだけで お子さんは、“安心感”を得ることができて、 また、そこから落ち着いて、その後の具体的な解決策や 対策について考えることができます。 ただし、お子さんが そのイヤだった出来事について 話したがらない場合は、お子さんの思いを 尊重して、 「いつでも聞くよ」というスタンスで 待ちましょう。 ::: もう一つ、例をご紹介すると…、 例えば、お子さんが 自信を失って 落ち込んでいる時。 「そんなことないよ~大丈夫だよ!」と励ましたくなりますが… 実は コレも、レジリエンス教育の観点から見ると、 ちょっと違うみたいです。 この場合も、『自信がない、不安だ』というお子さんの 気持ちを受け止め・寄り添って、 「自信無いのか…そういう時もあるよね。 でも、ママ(パパ)は、どんな時も、 がんばるアナタが素敵だと思うよ!」 …というような 声かけが 良いみたいですね。 ::: レジリエンスを育てる声かけのポイントは、 やはり、ネガティブな感情を 無視したり 否定したりしないこと。そして、大きな安心感に守られた中で、 ネガティブな感情と向き合い・耐えて、 対処できるチカラを育てていく…、ということなんですね。 ::: ある研究では、この「レジリエンス教育」を実践していくと 心の回復力に加えて、「どんなことがあっても 自分は大切な存在だ」という“自尊感情”や、 「自分はやれるんだ」という“自己効力感”も向上する、 という結果が 出ているそうです! …長い人生、お子さんの歩む 道の先には、 きっといろいろなことが 待っていると思います…! ぜひ パパママも、ご自分のレジリエンスを意識しながら お子さんへの声かけを 工夫してみてはいかがでしょうか。 |
|
2025年3月14日
『防犯ブザーのこと!』4月から 小学校にあがるお子さん・保護者のみなさんは
学習用具など 様々な準備が あると思いますが、 ピカピカのランドセルに、付けておくと安心なのが、 「防犯ブザー」!近年では、様々な機能が付いた防犯ブザーが 登場していて、種類も豊富になっていますが、 その中から どんなものを選べばよいのか、 今日は、簡単に チェックしてみましょう。 ::: まず 防犯ブザーを選ぶ時に 大切なのは、 お子さんが 実際に使う場面を よく想像すること♪ そのためには、こちらの 3つのポイントをチェックします。 ① その子にとって 使いやすく、持ち運びやすいもの。 ランドセルに取り付けやすい 吊り下げタイプや、 コンパクトなキーホルダー型などがありますので、 お子さんの 普段の行動パターンを振り返って、 選んでみましょう。 ② ブザーの音量 一般的には 100dB以上のものが 望ましいとされていますが、 あまり大きな音は 怖いという お子さんもいますよね。 事前に確認して、十分な音量で、かつ、 お子さんに合ったものを 選びましょう。 ③ 機能性 防犯ブザーには 音が鳴る以外にも、 GPS機能や自動通報機能、ライト機能など、安全性・利便性を 高める 様々な機能が搭載されているものがあります。 欲しい機能がついているか、よく比較検討する必要が ありますが、逆に、機能が多すぎると操作が複雑になって、 お子さんが使いにくくなってしまうこともあります。 “本当に必要な機能”を 見極めましょう。 ::: そのほか、電池式か・充電式か、大きさやデザイン、 カラーなどもお子さんと一緒に 選ぶと良いと思いますが、 防犯ブザーについて よく言われるのが、 「みんな持っているけれど、本当に役に立つの?」 という問題…。実際のところ、子どもたちがイタズラで ブザー鳴らすことも多く、音を聞いても 「あぁ、また鳴っているナァ」と思う大人も多いそうなんです。 でも、防犯ブザーは「付けている様子を見せること」に 意味があると言われます。例えば、犯罪者の目線を 想像すると…防犯ブザーを持っている子と・そうでない子、 どちらが狙いやすいでしょうか…? つまり、“抑止力”に なり得ます! また、子どもが走っているのを見た時、大人は、 何も鳴らしていなければ、ただ「子どもが走っている」と 思いますが、ブザーを鳴らしながら走っていれば、 「子どもが 走って逃げている」と気付いて、 早めに 助けてもらえるかも知れません! ::: 小さな防犯ブザーですが、やはり、効果は大きいものです。 そして、小学校の 中・高学年になって 「防犯ブザーの使い方を忘れてしまっていた」 なんていうお子さんも、是非、この春を機に、 使い方やその効果について、 おさらいしてみては いかがでしょうか。 |
前のページ 次のページ















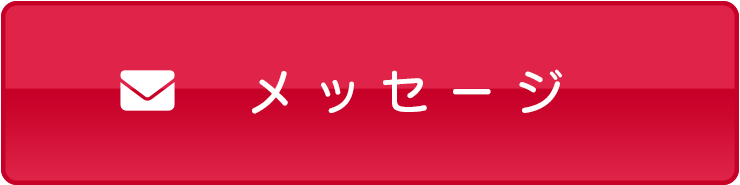

頭を抱えてしまう パパママも いるかも知れませんが…。
イヤイヤ期とは、こどもが 1歳~3歳ごろにかけて、
自己主張が強くなり、「イヤ!」を繰り返すことが増える、
その時期を指します。2歳ごろにピークを迎えることが多く、
“魔の2歳児”とも呼ばれますね~。
「お風呂もイヤ、着替えもイヤ、おむつ交換もイヤ…」
「やめて欲しいことを注意しても 聞いてくれない…」
一体、子どもたちの中では、何が起きているのでしょうか。
:::
イヤイヤ期の正体は、
心・知能が 急激に発達する、その変わり目の時期です。
そして、この時期(1歳~3歳くらい)のお子さんは、
とくに、“自律性が育つ”段階にあります。
自律性というのは、ある目的を達成するために
自分で計画し・行動する、そのチカラのこと。なので、
そんなお子さんの 心の中を のぞいてみると…
一生懸命、自分で考え・行動しようとしているところへ、
考えや予定に無かったことを、ママやパパから
アレコレ言われるので、「イヤ!邪魔しないで!」
と言いたくなる…、そんな気持ちなんだそうです。
:::
…とは言っても、中には、お子さんのイヤイヤが ツラく、
落ち込んでしまう親御さんも 少なくないですよね。
でも、ただ一つ、安心していただきたいのは、
世界中の2歳児たちが、「イヤ! NO!」と言っている、
ということです!“ウチの子だけじゃないんだ、
味方はたくさんいる”ということを、ぜひ、忘れないでほしいと思います。
:::
では その上で、できるだけパパママの負担を軽減できるよう、
どんな工夫ができるのか? というと…、
例えば、可能な範囲で、
時間に余裕をもつよう 心がけること。
イヤイヤ期のお子さんと向き合うには、
時間と心の余裕が必要ですよね。
時間に余裕があれば、パパママの心にも
少しは 余裕が生まれますし、お子さんの要求に
応えてあげられることも 増えそうです。
また、お子さんと落ち着いて会話するように心がけること。
小さなお子さんは、心の成長とはウラハラに、まだ、
自分の気持ちを 言葉で、上手に表現することができません。
なので、イヤイヤの強い言葉にも、反応しすぎないようにして、
お子さんが“本当は 何がしたいのか”を 聞き出すように、
時にはお子さんの気持ちを 言語化してあげながら、
落ち着いて会話をするのが オススメです。
:::
そのほか、先輩パパママの 対策・経験談も
参考になるかも知れませんので、ぜひ、近くに
先輩がいるかたは、相談してみるのも イイと思います。
そして、イヤイヤ期は、いつか必ず、終わりが来ます!!
みんなで支え合いながら、じっくり、乗り切っていきましょう。