[放送内容]2017年11月2日
小砂焼 秋の陶器市 水戸藩にも認められたという 小砂の土がこちら。  乾いていてサラサラ。 その都度、山で採ってくるの?と思ったら 「すでにあと100年分のストックがあります」とのこと! 写真はあくまでその一部なのです。 隣の丸みを帯びた石は「玉石(たまいし)」 ドラム缶を横にしたような機械のなかに 土、水、そしてこの玉石を入れて攪拌すると 中で土がまんべんなくつぶされるんですって。 そうして出来た泥水から水分を絞ると 粘土ができます。 これらを機械や手で練って 空気を抜いて、土のねじれを取り…… そして、ようやく ろくろや型を使って形作りへ。 藤田さんによると 小砂の土は比較的扱いやすいとのこと。 自分で粒子の細かさを調整できるそうなのですが 扱いやすいように調整もしているそうです。 (はじめての陶芸体験にもおすすめ) ---------- さて、形が出来たら自然乾燥。 この日は、秋晴れ! 外にたくさん並んでいました。 その後、800℃で素焼きをすると硬度を増します。 そして、ここで釉薬登場!! 小砂焼といえばコレ。  金色の斑点模様「金結晶」 その金結晶の釉薬がコチラ  ……赤茶色?? 「金」っぽさがなーい!! 器に塗っても、もちろんそのまま。 ちなみに左右のどちらかは黒の釉薬。 どっちがどっちか分からないくらい 見た目がそっくりです。 しかし、この後 釜で本焼き(1200℃!)すると ちゃーんと色が変わるんですよ! ただ、金結晶がどんな風に浮かび上がるかは 焼いてみないと分からないとか。 金結晶の小砂焼をいくつも作って来た藤田さんさえも 出方を予測するのは難しいそうです。 そのことをさらりと 「おもしろいよね」と話した藤田さん。 そうですね。偶然が生み出す唯一無二の個性が 金結晶の魅力なのだと思います。 ちなみに、釉薬と土は相性があって 仮に「あそこの釉薬いいなぁ!うちでも使おう!」となっても 合わないと金結晶がまったく出ないこともあるとか。 写真の釉薬は毎回、藤田さん自身が 一から調合しているそうですよ。 ----------------------------------- 素朴さと上品さが融合する「小砂焼」は 普段使いにも、プレゼントにもぴったり。 みなさんも運命の一品、見つけてみませんか? 秋の陶器市では 藤田製陶所を含めた町内外の窯元さんが出店。 小砂焼以外の陶器も並ぶそうです。 また、同じ小砂焼でも窯元さんによって 作り方や品物に個性があるとか。 ゆっくりじっくり見て回ってみましょう♪ また、当日はパフォーマンスイベントや 模擬店も楽しめます。 人気は もちつき! つくのも 食べるのもいつも大盛況です。 つく時間は特に決まっていないので つきたてを狙う方は、長居するつもりで 早めに行った方が良いかもしれませんよ。 買うだけじゃなく、作ってみたいっ!という方は ろくろ体験(1500円)、手びねり(1080円) 絵付け(540円)が体験できる 会場奥の「陶遊館」へ。 想い出をかたちにして 心に残る ひと時となりますように……♪ 【小砂焼 秋の陶器市】 日時:11月3日(金)・4日(土) 両日とも午前9時~午後4時 会場:藤田製陶所 入口(那珂川町小砂2710) ☆小砂焼体験は奥の「陶遊館」にて お問い合わせ:0287-93-0703 ---------------------------------------- 【ドングリ交流会 10th】 よろこびの森を散策しながら、 松ぼっくり・栗のいが・木の枝や木の実を採取して かざり炭をつくりましょう! できあがった炭をガラス瓶に入れれば完成。 素敵なインテリアとしてお家に飾ってくださいね♪ 昼食では大きな釜で炊いた ごはんを食べます! 日時:11月5日(日)午前10時~午後3時頃 会場:よろこびの森 ※案内板アリ (那珂川町小砂3691 岡倉様宅に隣接) 雨天時は小砂コミュニティセンターに会場変更 服装:作業しやすい服、靴、軍手 参加料:小学生以上 おひとり 1,000円 (材料費、昼食代、保険料込み) ☆飛び入り参加OK 会場案内など、ご質問は 那珂川町林業振興会 担当者 rinnsinn214@yahoo.co.jp まで。 ---------------------------------------- 2017年 春の陶器市での もちつき  |
























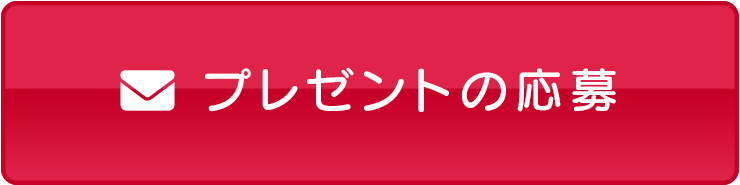
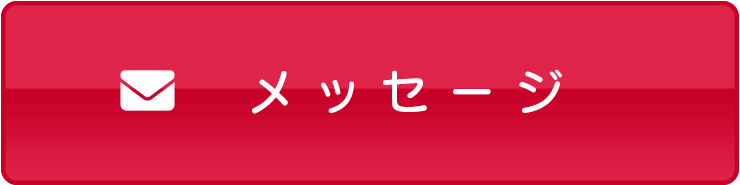



藩内で焼物を作ろう、となったときに
焼物に適した土を捜し歩き、結果、発見されたのが
小砂(こいさご)地区の土でした。
そこから誕生したのが「小砂焼」です。
その後、次第に窯元が増えていき
現代へと続いています。
現在、小砂焼の窯元でもっとも歴史あるのは
約160年続く『藤田製陶所』。
ここでは、毎年 春と秋に
小砂焼の陶器市が開かれています。
今回は、藤田製陶所 6代目の
藤田眞一さんに小砂焼のこと、陶器市のこと
お話を聞いてきました。