[番組で紹介した情報]2025年1月31日
『赤ちゃんと爪切り♪』 |
|
2025年1月24日
『朝のグズグズ・イライラ解消法?』朝は 忙しいのに…、
お子さんが なかなか起きてこなかったり、 やっと起きても なんだかノンビリしていたり…。 そんな様子に イライラしながら、 送り出したあとは 毎日グッタリ、、、 というパパママ、少なくないと思います~。 では一体 どうして、お子さんは朝、 シャキッと起きて動き出せないのか? 今日は その理由・ヒントを探ってみましょう。 ::: まず、お子さんが すぐに目覚められない・動き出せない理由、 それは きっと… “体と心の準備が整っていないから”。 「体」の準備不足は、例えば 睡眠が足りていなかったり、 そもそも 朝が弱い体質だったり…ということもありますが、 「心」の準備不足については、 朝・目覚めた時に“自分が起きて動き出す”という “未来のイメージ”が持てず、 心理的な抵抗があるから…かも知れません。 ::: では、その準備を整えるにはどうすればよいのでしょうか? まず、「体の準備」として 有効なのは、 カーテンを開けて、太陽の光を浴びること。 朝の光を浴びると セロトニンという目覚めのホルモンが出て、 体が動きやすくなります。 そして、布団から出られたら お水を飲む、顔を洗うなど、 目が覚めるような行動を 促すのもイイですね。 ::: そして、「心の準備」としては、日頃から、 朝・出かけるまでに やるべき事柄、 それにかかる時間などを おさらいして、 いわゆる“納得感”を得ておくこと。 そして、実際に目覚めた時、“起きて動き出す自分”を イメージできるようにすることが 大切です。 小さいうちは 時間の把握が 難しいかも知れませんが、 少しずつ 覚えていけたらいいですね。 ::: また、「朝は布団の中で しばらく ゴロゴロしないと起きられない」という子も いると思います。 これは 決してサボッているわけでなく、 そういう“体質”の子も 一定数 いるのだそうです。 なので、この場合は 最初から、 “布団の中でゴロゴロする時間”も準備に必要な時間と考えて、 その分 早めに起こしてあげるようにすると、 パパママのイライラも、一つ解消できるかも知れません。 ::: さらに、朝のイライラを増やさないために、 時には パパママが 頑張りすぎないことも、大切です。 例えば、「早く朝ごはんを食べてくれないと食器が洗えない!」 …と思うかも知れませんが、 「食器は あとで洗えばOK」と思うだけで、 ちょっと、心に 余裕が生まれるかも知れません。 ::: その子の体質や 心の準備に 寄り添いつつ、 パパママの 希望も叶えながら、気持ちよく 1日のスタートを切るために 出来ること…。 親子で 少しずつ 見つけてみては いかがでしょうか。 |
|
2025年1月17日
『マタニティマークを知ろう♪』マタニティマーク…「そんなの知っているよ~」
という方も 多いと思いますが、 一方で、妊娠の経験が無かったり、身近に妊婦さんがいないと なかなか見る機会・知る機会が ないものですよね。 今日は そんなマタニティマークのアレコレについて 改めて見てみましょう。 ::: マタニティマークは、まぁるいピンクのハートに ママと赤ちゃんのイラスト、そして、 「おなかに赤ちゃんがいます」というメッセージが添えられた 可愛いマークが 一般的ですね。 これは 厚生労働省が、 「妊産婦にやさしい環境づくり」の一環として、 2006年3月に、公募によって 決定したものです。 とくに、外見からは判別しにくい妊娠初期の妊婦さんに対する 周囲の理解を得ることを 主な目的に、 母子手帳と一緒にキーホルダーやステッカーが 無料で配られるほか、自治体によっては 保健センターや出張所でも 無料配布していたり、 電車を利用する時には 駅の事務室に申し出れば、 マタニティマークを 無料で もらうことができます。 ::: また、厚生労働省が提供しているマタニティマークのほか、 オリジナルデザインの マタニティマークや 人気キャラクターのデザインで、市販されているものもあります。 お気に入りのデザインを選んで 持ち歩くのもイイですね。 ::: そして、マタニティマークは、 「妊婦さんにやさしい心遣いを…」という願いから 作られたものですが、多くの人が出入りする 公共の場所では、周囲への配慮が 必要なこともあります。 外見ではわからない障害や 体調不良を抱えている人、 不妊治療などで、つらい気持ちでいる人もいるかも知れません。 公共の場には 様々な立場の人がいるということを 頭に入れておきましょう。 ::: また、残念なことに… マタニティマークを付けていたことによって 不当な嫌がらせをうけた、といった事例もあって、 「マタニティマークを付けるのがこわい」という人も 少なくないようです。 でも 実際、マークに気がつけば、 気遣ってくれる人が ほとんどです! 常に見える場所に つけないとしても、 急な体調不良など、緊急時の備えにもなりますので、 必要な時・すぐ出せるよう、 バッグなどに付けておくとイイですね。 ::: …ということで、今日は、マタニティマークにまつわる ちょっと ネガティブなお話しも してしまいましたが、 様々な アンケート調査の結果などを見ると、やはり、 マタニティマークのおかげで、「周りから助けてもらえた!」という ポジティブな意見が 大多数です。 みんなで、赤ちゃんと ママの体を守っていくためにも、 今後も マタニティマークを上手に 活用していきましょう☆ |
|
2025年1月10日
『みんなで学ぼう 正しい鼻のかみかた!』この時期は、とくに 風邪をひきやすかったり
これからは 花粉の季節もやってきますので、お子さんの 鼻水・鼻づまりが気になるかたも 多いのではないでしょうか? 鼻をかまずに放っておいたり、間違った鼻のかみ方をすると 中耳炎や副鼻腔炎などの リスクが高まります。 そこで きょうは、「正しい鼻のかみかた」を みんなでおさらいしてみましょう! ::: まず「正しい鼻のかみかた」の ポイントは… ① 片方ずつ、反対側の鼻の穴をふさいで、かむ。 ② しっかり鼻水を押し出すために、口から十分に息を吸う。 ③ ゆっくり、少しずつ かむ。強くかみすぎない。 どうでしょう… 皆さんは きちんと出来ていますか? あまり勢いをつけてしまうと、 鼻の粘膜が傷ついたり、耳が痛くなったりします。 また、両方の鼻を 一緒にかんでしまうと 逆に、鼻水が奥へ引き込まれやすく、 副鼻腔炎の原因になることもあるそうです。 大人の皆さんも、自分の鼻のかみ方はどうか… チェックしましょうね。 ::: そして、お子さんが 自分で鼻をかめるようになるためには やはり、練習が必要です。練習を始める時期は、 お話ができるようになる頃か、大人の動作のマネが できるようになってからがオススメです。 では、その練習方法ですが… 【その①】 鼻から息を吐く感覚を おぼえるために、 ティッシュを1枚、二つ折りにして 顔の前に垂らし、 鼻の息だけで ティッシュを 揺らしてみましょう。 この時、片方の鼻の穴をふさいで、 もう一方の鼻の息だけで 揺らすようにします。 最初は ママやパパが お手本を見せてあげましょう♪ 【その②】 次に、小さく丸めたティッシュを お子さんの鼻の穴につめて 鼻の息だけで ティッシュを飛ばす 練習をします。 この時も、やはり片方ずつ、行ないます! 丸めたティッシュが大きすぎると 鼻の中を傷つけてしまいますので お子さんの様子を見ながら 加減してくださいね。 (…見た目は ちょっと オモシロイですが、マジメな練習でーす!) こうした練習をしていくと、 自然に上達する子が 多いようです♪ ::: ちなみに、もっと小さなお子さん(新生児など)は もちろん 自分で鼻をかむことは できませんので、 肌に優しく衛生的な 綿棒やガーゼ、 柔らかいティッシュなどを使って、パパママが こまめに鼻水を 拭いてあげましょう。 鼻水が固まってしまった時には、 蒸しタオルなどでほぐしたり、 お風呂のタイミングで、やさしく取り除きます。 また、鼻水を吸い取るときには、赤ちゃん専用の チューブやスポイトで 丁寧に。 必ず、専用の吸引器具を 使ってください。 ::: 鼻水を放っておくと、健康リスクのほか 睡眠や集中力にも影響してしまうと言われていますので、 鼻をかむことは、とても大切です。 ぜひ早いうちから、正しい鼻のかみ方を身につけて みんなで 健康に過ごしましょう☆ |


















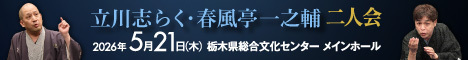





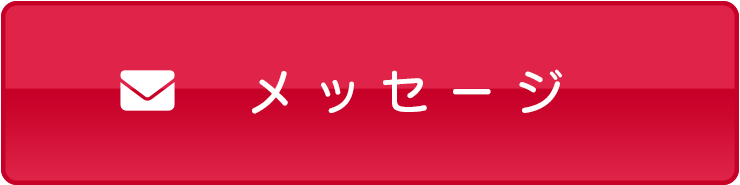

小っちゃくて、薄~くて、可愛いんですよね♪
ですが、とくに生まれたばかりの赤ちゃんは
新陳代謝が活発で爪が伸びるのも早く、
こまめに お手入れをする必要があります。
今日は、赤ちゃんの爪切りは いつから行なえば良いのか、
爪切りに使うアイテムなど、お話ししてみたいと思います。
:::
まず「いつからお手入れすれば良いか?」ですが、
赤ちゃんの爪はママのお腹の中にいる時から成長していて、
生まれた時、すでに 伸びていることもあります。
出産直後に、一度チェックしてみましょう。
:::
その後も、爪の伸びるスピードには個人差がありますが、
早い赤ちゃんでは、3~4日に1回、
少なくとも 週に1回は チェックしたいところ。
赤ちゃんの爪は、伸びたままにしておくと、
自分の顔を引っ掻いて 傷つけてしまったり、
爪の間に ゴミがたまると、衛生的にもよくありません。
また、爪が衣類などに引っかかって 割れてしまったり、
お世話をするママ・パパが 引っかかれてしまう
リスクもありますので、こまめにチェックしましょうね。
:::
そして、爪切りに使うアイテムは、
赤ちゃん用の爪切りと、ヤスリです。
(赤ちゃんの爪は、薄く・やわらかいので、
大人用の爪切りでは うまく切るのは ムズカシイんです。)
とくに 生まれたばかりの赤ちゃんには、
「新生児用」として売られている、
刃先が小さく・丸くて安全な“爪切りバサミ”が オススメ♪
生後6か月頃くらいになって
爪が厚くなって来たな~と思ったら、
「ベビー用」の 爪切りを使います。
明るい場所で、赤ちゃんの指を ママ・パパの手で
しっかり固定して、深爪に気をつけながら、
少しずつ、丁寧に 切っていきましょう。
:::
また、赤ちゃんの爪切りを行なうベストなタイミングは、
お昼寝中です。寝ている間は 暴れる心配が少なく、
比較的・安全に行なうことができます。
そして、爪を切る時の 心構えとしては、、、
“一度にすべての指の爪を 切ろうとしないこと”。
…早く終わらせたい気持ちは 山々ですが…、
途中で 赤ちゃんが動いてしまって、
思うようにいかないことも 多いです。
複数回に分けても大丈夫なので、“切れる分だけ切ったら、
残りは また明日…”という感じで、気楽に構えましょう。
:::
そのほか、赤ちゃんが 爪切りをしても嫌がらない体勢や、
タイミング、ご機嫌の取り方など、
“研究材料”は いくつもあると思います☆
赤ちゃんと一緒に過ごしながら、
お互いに心地の良いパターンをぜひ探ってみてください☆