[番組で紹介した情報]2025年6月20日
『水の事故を防ごう!』 |
|
2025年6月13日
『赤ちゃんの 虫よけ対策☆』初夏から夏は、お外での遊びも楽しくなって
赤ちゃんとのお出かけも増えると思いますが、 そうすると心配になるのが… 蚊などの「虫さされ」! きょうは、虫さされに注意しなければならない理由や 虫よけアイテムなどを チェックしてみましょう。 そもそも、赤ちゃんは大人よりも、 蚊に刺されやすいと言われています。 蚊は、生き物の 汗や熱を察知して 近寄ってきますが、 大人よりも体温が高く・汗をかきやすい 赤ちゃんは、 ターゲットにされやすいんです。 また、赤ちゃんは、蚊に刺された経験が少ないことから、 かゆみや腫れが 大きく出てしまうこともあります。 そして、赤ちゃんは自分でガマンすることはできませんので、 掻きむしってしまったり、それが 蕁麻疹や とびひなど重症化することもあるので、やはり、 そもそも 蚊を寄せつけない工夫、虫よけ対策をすることが 大切になってきます。 そして、虫よけ対策で まず思い浮かぶのは、 市販の「虫よけスプレー」。 ですが、赤ちゃんの肌に使用できるもの、 そうでないものがありますので 注意しましょう! 虫よけ、いわゆる「忌避剤」には 種類があって、 赤ちゃんが使用できないのは、 「ディート(DEET)」と呼ばれる忌避剤です。 このディートが使われている虫よけは、効き目は強いのですが、 濃度の薄いものでも、生後6か月以下の赤ちゃんには、NG! 生後6か月以上でも、1日1回の使用制限があります。 一方、赤ちゃんでも使えるのは、 「イカリジン」という成分が使われている 虫よけ。 年齢や 回数に制限がなく、生後間もない赤ちゃんでも 使用できます。ただ、ディートに比べると “有効な害虫の種類”が少ないと言われているので、 そのあたりは理解しておきましょう。 ちなみに、オーガニックの虫よけは、そのイメージから 「赤ちゃんにも使える」と思うかもしれませんが、こちらも、 年齢によって 使用回数などに 制限があるものもあります。 使用する前には必ず、製品の注意書きを しっかり読んで、 確認するようにしましょう! また、虫よけスプレーのほか、 赤ちゃんの衣類やベビーカーに貼るタイプの虫よけもありますね。 肌への刺激がないので、安心感があります。 さらに、眠っているあいだの虫よけには、 物理的に虫をシャットアウトできる、「蚊帳」もオススメ! ワンタッチで開く、小さなテントのような、赤ちゃん用の カワイイ蚊帳が2,000~3,000円くらいから 売られています♪ 意外と大事な、赤ちゃんの虫よけ対策。 これから夏休みなど お孫さんが遊びに来る♪という おじいちゃん・おばあちゃんも、ぜひ、 チェックしてみてはいかがでしょうか。 |
|
2025年6月6日
『こどもはナゼ 歯磨きがキライなのか?』毎年 6月4日~10日までの 一週間は
「歯と口の健康週間」です♪ 歯磨きは 丈夫な体の 基礎づくり… ですが、 “こどもが 歯磨きを嫌がるので 困っている!”という パパママの皆さん、多いですよね? でも、お子さんが嫌がるのには、 それなりの、理由があるようです。 きょうは、「どうして そんなに歯磨きが イヤなのか?」… その代表的な3つの理由と 対処法について探ってみましょう。 まず 歯磨きを嫌がる理由・1つめは…、 「歯ブラシが口に入る、異物感がイヤ!」 確かに… 口に入った異物が 上下左右に動くのは、 やっぱりキモチワルイですよね? なので、まずは その感覚に慣れてもらうことが 大切です。 その第一歩としては 例えば…、 お子さんに 赤ちゃん用の歯ブラシを渡して、 好き勝手に、いじってもらうこと♪ そして、安心したところで、親が歯磨きをしているのを 見せたりすると、マネをして、徐々に 歯ブラシの感覚に慣れていく子も 多いようです♪ 続いて 2つめは…「仕上げ磨きが、くるしい!」 仕上げ磨きの時、おとなの感覚でお子さんの歯を磨こうとすると ちょっと痛いと感じることが あるようです。 なので、仕上げ磨きの時は、歯ブラシを 軽いチカラで 鉛筆を持つように持って、少しずつ、磨きましょう。 また、仕上げ磨きの時、仰向けで ずっと口を開けていると、 アゴが疲れたり、唾液がノドにたまって 苦しい…と感じる子も 多いようですから、タイミングを見て 唾液を吐き出させたり、 休憩をとるよう、うながしてあげましょう♪ そして 最後の3つめは… 「歯磨きの時の ママ・パパが、コワイ!」 …歯磨きをさせるために、時には 押さえつけたり、 叱ってしまうコト… ありますよね~。でも そうすると、 “歯磨きの時には ママ・パパが恐くなる!” というイメージがお子さんの中に、染みついてしまいます。 ですから、歯磨きタイムには、イメージが悪くならないように…、 ママ・パパも ニッコリ笑いながら、 楽しいスキンシップの時間になるよう、心がけてみましょう。 また、番外編として…、 いわゆる“イヤイヤ期”に入ってから 急に 歯磨きを嫌がるようになった、という子も多いようですね。 でも、そんな時には、イヤイヤ期・特有の、、、 自分で何でもやりたがる性質を 逆手にとって…、 敢えて、正しい歯磨きの仕方を シッカリ教えてしまう! というのも、一つの方法です♪ …あまり神経質になるのも 良くありませんが、 虫歯予防のためには、やはり、なるべく 早く対処したいところ。まずは、お子さんが “どうして歯磨きがイヤなのか???”その理由を ていねいに聞き取るところから、始めてみてはいかがでしょうか。 |
|
2025年5月30日
『 折り紙の魅力♪』これからの雨の季節は、
お子さんも おうちの中で遊ぶ時間が 増えますね。 おうちで楽しめる遊びは 色々ありますが、 中でも、「折り紙」は日本伝統の遊びであり、 手軽で・クリエイティブな遊びの一つ♪ きょうは、そんな折り紙の魅力について お話ししてみましょう。 まず 折り紙は、紙さえあれば、場所を取らずに、 いつでも・どこでも 楽しむことができますね! プリントやチラシを 再利用することもできますし、 100円ショップでも 様々な種類の折り紙が安く手に入ります。 また、大きなオモチャと違って、持ち運びも簡単♪ 旅行や外出先でも、場所を選ばず遊ぶことができます。 そして、折り紙は、知育玩具としても非常に優秀で、 お子さんの想像力や空間認知能力、集中力などを育ててくれます。 例えば…、 最初は 折りかたを教えてもらったり本などを見ながら 手順に沿って 折り始めますが、慣れてくると だんだん、折り方をを「記憶」して、 さらに 完成形を「想像」しながら 折れるようになって、記憶力・想像力が 育まれていきます。 また、折り紙の本には 複雑な図形が描かれていますが、 その図形に慣れる過程では、 平面図から立体的なかたちを読み取り・完成させる、 「空間認知能力」も、育っていきます! そして、よりキレイに仕上げるためには どうすれば良いかを考えれば「思考力」や 「工夫」も生まれますし、さらには、カラフルな折り紙を 使うことで「色彩感覚」も養われたり…と、遊びながら、 あらゆる能力を 複合的に育むことが出来るんですね! 同時に、折り紙を折ることは、 脳の活性化にもつながることが分かっています。 例えば、指先の運動や感覚の 制御に関わる「前頭葉」、 色や形を認識する「側頭葉」、 形のバランスを 立体的にとらえる「頭頂葉」…など、 折り紙を折ることで、脳のさまざまな場所が 刺激されます。 また、“折り紙を折る”という作業に 集中・没頭すると、 脳が「瞑想」や「マインドフルネス」と呼ばれるものに近い 状態になって、ストレス解消にもなると 言われています! (ぜひ 大人も一緒に、楽しみたいですね☆) そんな折り紙は、日本だけでなく世界中にも広がって たくさんのファンがいると 言われていますが、 その折り紙の魅力を 世界に伝えたのは…、 ほかでもない、栃木県・上三川町出身の 創作折り紙作家、 吉澤章さんです。 吉澤さんの活動によって世界の共通語となった「ORIGAMI」、 そして、一枚の紙と お子さんの小さな手から生まれる、 様々な可能性…☆ 改めて、ぜひ注目してみてはいかがでしょうか。 |
|
2025年5月23日
『 中間反抗期!?』反抗期…というと、2才~3才前後の
「第1次反抗期」(いわゆる イヤイヤ期)、 そして、思春期の「第2次反抗期」を思い浮かべると思いますが、 この 1次と2次の、あいだの時期にやってくるのが 「中間反抗期」。小学校の低学年~中学年ごろ、 反抗的な態度が表れやすくなるのだそうです。 (ご存知でしたか?) そして、中間反抗期にはどのような言動が多くなるかと言うと… ・何かと口答えが増える、屁理屈を言う、ウソをつく ・イライラした様子で、パパやママと会話をしたがらない。 ・注意しても 聞こうとしない。 ・パパやママが 手伝ったり世話をするのを 嫌がる。 …などがあります。 自分の子どもの頃を 思い出して 「そんなコト あったかなぁ?」と思う人も多いかも知れませんが、 実際に 中間反抗期は、第1次・第2次反抗期ほど 激しく表れないことが多く、いつの間にか 過ぎてしまうケースも あるようです。 でも、そんなお子さんの言動に カチンときたり、 中には、突然の変化に ショックを受けてしまう親御さんも いるようなので、これからこの年頃を迎えるお子さんがいる方は 「中間反抗期」という 言葉だけでも知っておくと、 そのショックを やわらげることが 出来るかも知れません。 そして もちろん、中間反抗期は、 第1次・第2次反抗期と同じように、 お子さんの心の成長において、とても大切なもの。 自我や自立心が育ち、自分で考えて行動しようとする気持ちが 強まることで、パパやママの言いつけに従うことを 嫌がるようになるんです。なので、 この時期に 反抗的な言動が見られるということは、 「心が育っている証拠」とも言えます。 とは言え、反抗的な お子さんの態度に接すると どう対処すべきか、考えてしまいますよね! なかなか難しいとは思いますが…、 試してみたいのは、いったん深呼吸して、 お子さんの態度を、おおらかに受け入れること。 この時期のお子さんは、とにかく「自分を認めて欲しい」という 気持ちが強いので、まずは「○○ちゃんは そう思うんだね」と 受け止める態度を 示すことです。 でも同時に、人を傷つけることや 間違っていることに対しては毅然とした態度で、 「そういう言い方をされると 悲しいな」とか 「やるべきことは 自分でしようね」というように 大事なことはシッカリ伝える、というのも大切です。 目の当たりにすると ビックリしてしまいそうですが 中間反抗期は、お子さんの 心の成長のあらわれ。 パパママも 寄り添い・模索しながら、向き合ってみてください☆ |
前のページ 次のページ















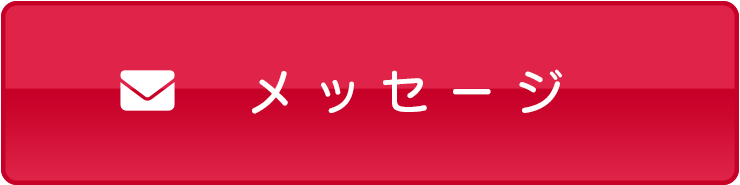

毎年夏になると、プールや海・川などで
子どもが溺れて…という悲しいニュースが増えてしまいますよね。
子どもたちを水の事故から守るために、
改めて、注意点をおさらいしてみましょう!
まずは、「子どもは 大人よりも 溺れやすい」ということを
よく認識しておきましょう。とくに小さな乳幼児の場合、
水の深さが10センチ程度だったとしても
溺れてしまうことがあります。
そして、実際に人が溺れてしまう時には、
音もなく沈んでしまうことが 多いと言われています。
ちょっと怖いな~と感じますが、
人は咄嗟のことになると 声が出なかったり
動けなくなってしまうことが多くて、
ドラマのように バシャバシャ暴れたり
「助けて!」と叫んだりすることは ほとんど無いと
考えておいたほうが良いかも知れません。
そうしたことからも、水遊び中のお子さんからは
決して目を離さず、必ず 保護者が見守ること。
その場を離れたいときには、
お子さんも一緒に連れて、移動するようにしましょう。
また、場所ごとに、様々な注意点があります。
プールの場合は、飛び込んだ時に事故が起こることも多いので、
プールには 静かに入らせましょう。また、
吸い込まれる危険のある「排水口」に近づいたり、
監視員の目の届かない 遊具の下などには
潜り込まないように注意します。
そして 海での水遊びは、必ず、
監視員やライフセーバーのいる海水浴場の
「遊泳許可範囲」内で 遊ぶこと。また、堤防や河口、
岩場などの近くでは、「離岸流」と呼ばれる
沖に向かう潮の流れが発生します。これに巻き込まれると、
あっと言う間に 沖へ流されてしまうので、近づかないように!
子ども用のライフジャケットを着用させると 安心です。
そして、川で遊ぶ場合も、
ライフジャケットの着用が推奨されています。
川の流れは、ゆるやかに見えても かなり速い場合があったり、
深さも 見た目では測れないので、より注意が必要です。
とくに上流で雨が降っているときや 増水しているときなどは、
流されてしまう危険が高いので、近づかないようにしましょう。
また、海や川で遊ぶ時には、
「水遊び用の靴」が オススメ!
ビーチサンダルなどは脱げやすく、
“脱げて流された サンダルを追いかけて…”という
事故も多いので、ケガを予防するためにも、
サイズの合った・脱げにくい、水遊び用の靴を 用意したいですね。
そのほか、子どもの様々な 水の事故については、
「こども家庭庁」のWebサイトにも 掲載されています。
「こどもの事故防止ハンドブック」の中にある
「水まわりの事故」のページも、ぜひ一度チェックしてみてください☆