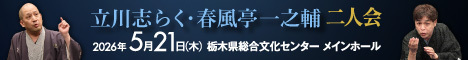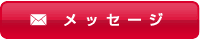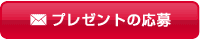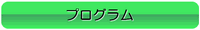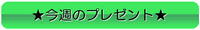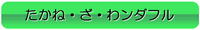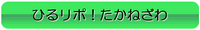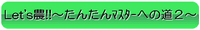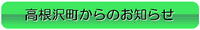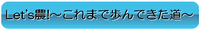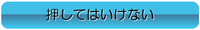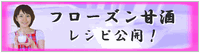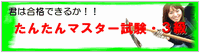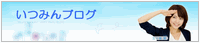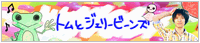[今週のプレゼント]2013年7月24日
☆番組ステッカー☆ メッセージをいただいた方の中から抽選で3名様に『高根沢たんたんCafe』オリジナルステッカーを差し上げます。
newサインにも慣れてきた、いつみん&トム!! 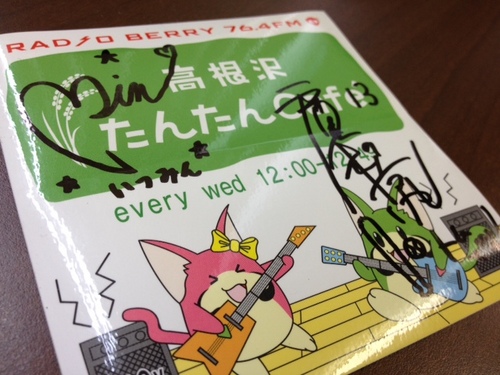 もしかしたら。。。あなたの元に届くステッカーにも。。。いつみん&トムのnewサインが。。。
|
[たかね・ざ・わンダフル]2013年7月24日
藍の生葉染め今回は、藍の生葉染めを体験しました。
教えてくださったのは、高根沢町で活動している里山文化の会の大野恵子さんです。  私が手に持っているのが、今回染め上げたシルクのスカーフです。
夏色に染まっていい感じに仕上がったと思います。 「生葉染め」は、その名の通り、生の葉を使います。 色は藍染めよりもかなり薄く、夏空のような水色に染まるのが特徴です。 これが藍の葉です。  朝早くに畑へ行って、朝露が乾かぬうちに摘むのが良いとされています。
この葉に塩を振り、よく揉みこみます。 全体がしんなりしてきたら、 水を張ったトレイに汁を絞り出し、染色液を作ります。  ここにシルクのスカーフをいれ、液の中で静かに動かたのち、
取り出して絞り、広げて空気に触れさせます。 すると、薄いみどり色だったのが、淡い水色にふわっと変わりました。 これは酸化による色の変化だそうです。 この染色液に浸して、取り出して空気に触れさせを2~3回繰り返します。 何度もやるほど色が濃くなりますが、やりすぎるとくすんだ色になってしまうので、 どこで染めるのをやめるかの判断が重要です。 私は3回でやめることにしました。  自然のものを使って染め上げるので、2度と同じ色に染めることはできません。
色との出会いは一期一会なんですね。 そこが染物の魅力なんだと思いました。 体験したいというかたは、8/18(日)元気あっぷむらで体験ができます。 時間:朝10時~午後2時 料金:大人が2800円 、子どもが1900円です。 *染色に使用するシルクのスカーフ、昼食と温泉の入浴もセット 定員:先着20名 興味のある方はお早めに元気あっぷむらまでお問い合わせください。 |
[ひるリポ!たかねざわ]2013年7月24日
十割そば ひかりリポーターのトムです!
暑い夏はやはり、さっぱりしたものが 食べたくなりますよね~。 食欲減退する季節ですが、しっかり食べないといけません。 僕が今日おじゃましたのは、 高根沢町大谷にある『十割そば ひかり』です! 小さなお店なのですが、雰囲気はバッチリ。 高根沢の田園風景に合う木目や畳の内装。 客席は15~16席ほど(?)  このお店で長年蕎麦打ちをしているのが、板橋さんです。
県内、県外から仕入れた極上のそば粉を使って、 十割そばを手打ちしています。 十割そばというのは、繋ぎの粉を使わない、 完全にそば粉100%ということです。 十割そばというのは、繋ぎがないため打つのが難しいんです。 そんな手間暇のかかるお蕎麦を、 なんとこのお店ではいろんな種類のものが楽しめます。  今回中継の際に頂いた『ひかりスペシャル』はこちら。
何と一日4食限定。レアものですね~…!! 長野県の親田、栃木県馬頭、福井県越前、 それぞれのそば粉で、十割そばが綺麗に打たれています。 ノド越しがびっくりするほど爽快! 十割そばというと、長さが短くてザラザラでボソッとしたような そんなイメージですが、これは本当に十割かと思うほど、 美しい仕上がりでございました! 水だけで味わう「水そば」や、高級塩で頂く「塩そば」もついてます。  こちらは、2色になっている光雲(幸運)蕎麦。
黒い部分と白い部分がありますね~。 白の部分は更科(さらしな)蕎麦といって、 蕎麦の実の殻を使わないため、白いお蕎麦になるんです。 更科蕎麦を十割で打って貼り合わせるお蕎麦を打つ店は、 全国で指で数えるほどしかないんだそうな。 お店に毎日食べに来ているお客さんも、 「長野県の(某有名そば店)とココがトップクラスだな」との事。 がしかし、とても僕の舌では 味の“ニュアンス”を感じられず…。 蕎麦って…打つ人も研究熱心ですけど、 食べる側も、相当な修行が必要なんですね~…。 ******************** 『十割そば ひかり』 場所:栃木県高根沢町大谷98-3 電話:028-675-3944 営業:11:00~14:00 定休:木曜・金曜 ******************** 普通のお蕎麦では、なかなか蕎麦の香りって感じにくいと そんな風に思うんですが…  僕のグルメじゃない味覚でも確かに感じられたのは、 蕎麦の確かな本来の香りと、微かな甘さ。 そして、板橋店長のお蕎麦に対するこだわりの深さと、 高根沢の「手間暇かけて」をモチーフにした(?)、 野性的かつ丁寧な心意気です。 この『十割そば ひかり』のそばを食べれば、 目の前に、日光、那須連山、富士山の景色が 浮かび上がってくるような、そんなお蕎麦でした。 |
[Let's農!!~たんたんマスターへの道2~]2013年7月24日
~転作調査とは!~古より代々、
おひさまと、水と、土に感謝しながら 様々な農産物を作ってきた高根沢。 そんな高根沢の農業の魅力を広く伝え、 たんたんマスター見習いとなった 「いつみん」五十嵐愛が、更なる高みを目指し、 日々学び、挑戦、活躍するコーナー。 『Let's 農!!~たんたんマスターへの道2~』 今回は、まちで行っている調査記録の活動である、 『転作調査』というものについて学びました。  この転作調査という作業と仕組みについて教えてくれたのは、
高根沢町太田にある「農業技術センター 水田農業確立対策室」で働く、 阿久津さん(真ん中)です。さらに、岩本さん(左)も、 作業について教えてくださいました。 転作調査とは、お米の減反調査および、 転作確認を行う、管理作業のことです。 分かりやすく説明すると、 町で、販売するためのお米を栽培する場合、 「○○パーセント、田んぼをお休みして(米を作らないで)ください」 というものが決まっているので、きちんと田んぼがお休みしているか、 そして、その休んでいる田んぼで違った農作物が育てられている場合、 何が育てられているのかを確認しなければならないわけです。  なぜ、田んぼを全部使ってお米を作れないのかというと、
“販売用のお米”は、作りすぎると売れ残ってしまうわけです。 今の時代は、パスタやパン、うどん、蕎麦など、 いろいろな食材がお腹を満たしてくれるので、 必ずしもお米が100%必要な状況ではなくなってきているんですね~。 さらに、出荷量が増えすぎてしまうと、 相場の値段も下がってしまうため、農家さんたちは 「余ってしまう」「安くしか売れない」ということになり、 何の得にもならないというわけです。  つまりは、お米の需要と供給に伴って、
生産量・出荷量を調整する。という作業が きちんと現場で行われているのかどうかを、 確認するんですね~! 農家さんたちの無駄な労働や商売の非効率を押さえるための 立派な町の仕組みというわけです。 そして、その休んでいる田んぼがもったいないために、 「別の野菜を作って利益を得ましょう」ということで 田んぼを転作している場合、その作られている野菜の種類によって 交付金の金額が変わってくるため、しっかり確認する必要があるのです。 この作業は1週間続きます。そして、1日に80~100筆もの田んぼを 見回って、転作確認をするんです。 この地道な作業も、日本の農業の明日を支えているのですね。 |
[高根沢町からのお知らせ]2013年7月24日
【第27回高根沢町観光写真コンテスト参加募集】高根沢町観光協会では、町内の隠れた魅力を再発見することを目的に、
観光写真コンテストを開催します。 テーマは自由で何でもOK。町内で本人が撮影した未発表の作品であれば、どなたでも応募することができます。 応募点数はひとり5点まで、四つ切プリントしたものを高根沢町産業課内 高根沢町観光協会事務局へ持参してください。 申込み期限は9月30日までで、入賞者には賞品を贈呈します。 今まで気づかなかった高根沢町の魅力を撮影して、高根沢町観光写真コンテストにぜひご応募ください。 **************** お問い合わせ 高根沢町産業課商工観光担当 TEL:028-675-8104 **************** |